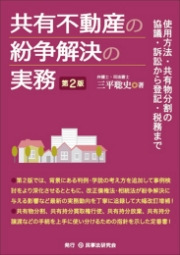【短期賃貸借保護制度(平成15年改正前民法395条)と借地借家法との関係】
1 短期賃貸借保護制度(平成15年改正前民法395条)と借地借家法との関係
平成15年の民法改正前の民法395条は、短期賃貸借保護制度を定めていました。今ではこの規定そのものが使われることは通常ありませんが、現在でも、この規定に関する解釈を活用することはあります。
本記事では、短期賃貸借保護制度と借地借家法が関係する場合の解釈論を説明します。
2 平成15年改正前民法395条の条文
最初に、改正前の民法395条の条文を確認しておきます。
平成15年改正前民法395条の条文
但其賃貸借カ抵当権者ニ損害ヲ及ホストキハ裁判所ハ抵当権者ノ請求ニ因リ其解除ヲ命スルコトヲ得
※民法395条(平成15年改正前)
登記の順番で抵当権と賃借権の優劣が決まる、という大原則に対して、例外を認めるルールです。つまり、後から登記した賃借権が優先されるという扱いです。ただし、この適用を受けるのは民法602条の期間を超えないもの(短期賃貸借)です。民法602条の内容については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|処分権限のない者による短期賃貸借(長期賃貸借との判別・民法602条)
3 短期賃貸借保護制度と借地・借家の解釈の結論(まとめ)
借地(建物所有目的の土地の賃貸借)や借家(建物賃貸借)の契約は、借地借家法(旧借地法や借家法)によっていろいろなルールが適用されます。
借地については、法定相続期間で最低限の期間が30年や60年と決まっています。借地、借家ともに、期間が満了しても、法定更新が原則でありそう簡単には契約が終了しません。また、借家は期間の定めがないタイプの契約も認められていますが、賃貸人からの解約はそう簡単には認められません。
このように借地、借家にはいろいろな特徴があるので、短期賃貸借保護制度の適用を受けられるか、逆に借地借家法のルールは適用除外にならないか、という問題が出てくるのです。
問題は複雑ですので最初に結論を整理しておきます。
<短期賃貸借保護制度と借地・借家の解釈の結論(まとめ)>
あ 長期/短期判定
ア 期間の定めなしケース
借地→法定期間の適用あり→自動的に長期扱い
借家→(法定期間なし)→(形式的判断で)短期扱い(+3年後には解約が認められる方向性)
イ (短期の)期間の定めあり
(期間5年以内の)借地→法定期間の適用なし→短期扱い
(期間3年以内の)借家→短期扱い
※期間の定めがあってもなくても法定更新(い)により実際の期間は長くなるから長期扱いにする、という発想もあるが、この見解は一般的ではない
い 法定更新(+建物買取請求権)の適用
差押後の更新については否定(抵当権者・買受人に対抗できない)
この内容については以下、順に説明します。
4 期間の定めがないケース→借地は長期・借家は短期扱い
(1)昭和39年最判→借家は短期扱い
まず、期間の定めがないケースについて説明します。
昭和39年最判は、期間の定めのない借家について、「3年を超えていない」という形式に着目して、短期扱いとしました。つまり、短期賃貸借保護制度を適用する、という結論です。
その結果、競売での買受人は貸し続ける必要があります。買受人としては解約(申入)をすれば借家契約を終了させられます。この点、借地借家法(借家法)では、解約申入のためには明渡料を支払うことも含めて正当事由が必要とされています。これに関して最高裁は、本来抵当権より劣後となるという事情が、更新拒絶や解約申入における極めて有力な資料となる、と判断しました。
つまり、建物の賃貸借が保護されるのは3年なので、借家契約が3年を超えていれば解約申入が認められやすい、という意味です。
昭和39年最判→期間の定めのない借家は短期扱い
あ 結論→短期賃貸借該当性肯定
・・・期間の定めのない建物賃貸借は、「正当事由」さえ存在すれば何時でも解約申入によりこれを終了させることができるのであつて、期間の到来まで解約の余地のない長期賃貸借(民法第六〇二条の期間をこえる賃貸借)とは異なるから、前記借家法の改正後においても、期間の定めのない建物賃貸借は民法第三九五条の短期賃貸借に該当すると解するのが相当である(大判・昭和一二年(オ)八五九号、同年七月一〇日判決、民集一六巻一二〇九頁参照)。
い 正当事由の判定→肯定方向に働く
けだし、かく解しても、抵当権の実行により建物を競落した者が賃貸借の解約申入を為す場合においては、民法第三九五条の短期賃貸借制度の趣旨は、前記「正当事由」の存在を認定する上において極めて有力な資料とすべきであるから、前記のように解しても抵当権の不当な犠牲において賃借権を保護することにはならないからである。
う 結論→民法395条適用肯定
そして、賃貸借の登記がなくても、賃貸家屋の引渡がなされた以上、右賃貸借をもつて抵当権者(競落人)に対抗しうると解するのが相当であるから(前掲判決参照)、本件建物賃貸借が民法第三九五条の短期賃貸借にあたるとした原審の判断は正当である。
※最判昭和39年6月19日
(2)昭和45年最判・借家は短期+借地は長期扱い
昭和45年最判は借地、借家(建物賃貸借)の両方について、期間の定めのないケースの判断をしました。
まず、建物については、期間の定めのない賃貸借を短期扱いとしました。昭和39年最判と同じ判断です。
次に、建物所有目的の土地の賃貸借(借地)については、期間の定めがないので、旧借地法により法定期間である30年が適用される状況でした。
詳しくはこちら|旧借地法における期間に関する規定と基本的解釈
そこで、民法602条の「10年」を超えることになるので長期扱いとする、と判断しました。つまり短期賃貸借保護制度は適用しない、という結論です。
昭和45年最判・借家は短期+借地は長期扱い
あ 期間の定めのない借家→短期扱い
右事実関係のもとにおいては、本件建物の賃貸借は期間の定めのない賃貸借であるから、民決六〇二条の定める短期賃貸借と解すべきものであり(最高裁昭和三六年(オ)第二八号同三九年六月一九日第二小法廷判決民集一八巻五号七九五頁、同四二年(オ)第四七七号第四七八号同四三年九月二七日第二小法廷判決民集二二巻九号二〇七四頁参照)、上告人が民法三九五条の規定により右賃借権をもつて被上告人に対抗することができるとした原審の判断は正当として首肯することができる。
い 期間の定めのない借地→長期扱い
・・・本件土地の賃貸借は建物所有を目的とする賃貸借と推認できるところ、期間の定めのないこの種の賃貸借の存続期間は借地法二条一項、三条の定めるところにより三〇年であるから、本件土地の賃貸借をもつて民法六〇二条に定める短期賃貸借とすることはできず、上告人は民法三九五条により右賃貸借をもつて被上告人に対抗することができないものといわなければならない(最高裁和年三五年(オ)第三三六号同三八年二月二六日第三小法廷判決裁判集民事六四号六六三頁参照)。
※最判昭和45年6月16日
5 期間の定めがあるケース→借地の法定期間の適用なし
(1)我妻栄・新訂担保物権法・借地の法定期間→適用なし
次に、期間の定めのあるケースについて説明します。借地については、法定存続期間として、最低30年(または60年)というルールがあります(前述)。そこで、期間5年の借地契約を締結した場合にはどうなるか、という問題が出てくるのです。
単純に考えると、法律上期間は30年(または60年)となるので、5年を超えることになります。そこで長期扱いとなる(短期賃貸借保護制度は適用されない)、ということになります。
しかし、判例(後述)も含めて一般的な見解は5年の借地契約として有効になる、と解釈します。つまり、借地法の法定存続期間は適用されないということにするのです。
まず、我妻氏はこの見解をとっています。
我妻栄・新訂担保物権法・借地の法定期間→適用なし
あ 借地法の法定存続期間→最低限となる(前提)
(a)借地法では、当事者が期間を定めなければ、賃貸借の目的が堅固な建物の所有かどうかによって、六〇年または三〇年に一定され、当事者が期間を定めても、右の区別に従って、三〇年または二〇年未満の期間は許されない。
いいかえれば、宅地の賃貸借を五年と定めることは許されない。
い 抵当権設定後の借地
ア 判例はみあたらない(前提)
第三九五条の適用についてどう解すべきであろうか。
第三九五条そのものが借地法で三〇年または二〇年(当事者の設定しうる最短期)と変更されたとみることはできないとする判例(大判昭和二・一・三一民六頁(判民二事件我妻、民法判例評釈I所収))は正当である。
しかし、どう解すべきかについて判例の積極的な見解は明らかでない。
イ 法定存続期間→適用なし
借地法の関係では、期間は、右のように、長いものに一定されるが、第三九五条の関係では、五年未満という約旨はそのまま効力を持続し(従って登記も可能)、その限度内で抵当権に対抗しうると解するのが正当であろうと思う。
ウ 法定更新→適用あり
(b)第三九五条の関係では宅地の賃貸借も五年以下と定めうるとするときは、その更新が問題となる。
競売開始決定の後は更新は認められないが、それまでは、借地法第四条の要件を必要とせず、二〇年ないし三〇年まで、当然に更新される、と解すべきであろう。
※我妻栄著『新訂 担保物権法』岩波書店1968年p341、342
(2)奈良次郎氏見解・借地の法定期間→適用なし
5年以内の期間を定めた借地契約について、奈良氏も同様に、形式論だと長期扱いとなることを指摘した上で、抵当権に劣後する賃貸借については5年以内の契約も可能であるという見解をとっています。1つの考え方として、借地法の一時使用目的の借地として法定存続期間の適用を排除する、ということも指摘しています。
また、そもそも借地については短期賃貸借保護制度が想定していない、という別の見解(発想)も紹介しています。
ところで、前述のように期間の定めがない借地契約では法定存続期間の30年(または60年)が適用されて長期扱いとなります。そのことと5年の借地契約だと30年にならずに短期扱いとなる結果はアンバランスな感覚もあります。この結果の違いについて、金融判例研究会では許容する意見が多数であった、という指摘もあります。
奈良次郎氏見解・借地の法定期間→適用なし
あ 形式論→法定存続期間適用により長期扱い(前提)
前述した期間の大原則に従えば、短期賃貸借といえども、一時使用を目的とする借地権でない限り、期間の約定が「定メサリシモノト看做」されるはずであるが、その意味では逆に、短期賃貸借イコール一時使用の借地権と解されない限り、民法三九五条による短期賃貸借の保護を受けられないとすることも、形式論理的には可能である。
い 一般的解釈→法定存続期間適用なし
ア 形式論の適用→否定
だが、抵当権者のいる場合に民法三九五条の適用が問題になるときには、一般的にはそのようには解釈しておらず、短期賃貸借である限り、一時使用かどうかを検討せずに、当然に民法三九五条の保護を受けるものと解している。
※奈良次郎稿/『金融法務事情893号』1979年6月p16
イ 法定存続期間の適用否定(5年内の期間の借地肯定)
換言すれば、抵当権設定登記後に成立する土地賃貸借については、少なくとも抵当権者の関係では、借地法二条は当然にはストレートに適用されず、当事者間の約定―といっても五年未満のものであるが―は効力を有するとみてもよいだろう。
ウ 一時使用目的を認める発想
考え方として、短期賃貸借の約定は、合理的である限り一時使用のための借地権に該当すると認定することも、十分考えられる。
とくに、判例上、借地期間一〇年のものでも―もつともこれが限度であるが―一時使用の借地権と認められた例(最判昭36・7・6民集一五巻七号一七七七頁、同昭43・3・28民集二二巻三号六九一頁、
同昭43・11・19判例時報五四五号六一頁など。もちろん、借地の目的、建物の構造・種類など、諸般の事情の認定はされている)もあることからみれば、その半分である五年で建物所有を目的とするとすれば、いちおう一時使用の借地権との推定を働かせることは可能であろう。
う 別の見解の紹介
清水(誠)・銀行取引法講座一○七頁は、短期賃借権の保護は、土地賃借権を考えず、建物賃借権のみを考えていた規定ではないかとの疑問を示す。
※奈良次郎稿/『金融法務事情893号』1979年6月p20、21
え 期間の定めなしケースとの比較
ア 期間の定めなしケース→法定存続期間適用あり(前提)
借地契約において期間を定めないときには借地法二条により、法律上三〇年または六〇年と定められると解するわけである。
イ 法定存続期間の適用の有無が異なる結果→許容
これと関連して、研究会(注・金融判例研究会)では、当事者間でたとえば五年の約定がされたとき、抵当権の設定登記のときには借地法二条がストレートに適用されないのに、同じ場合に、期間を定めないときは民法六一七条の適用を認めないで借地法二条をストレートに適用することの当否が論議されたが、借地法二条の規定の適用を排除する根拠がないというのが多数の見解であった。
※奈良次郎稿/『金融法務事情893号』1979年6月p21
6 法定更新(+建物買取請求権)の適用→差押後は否定
(1)昭和38年最判・差押後の借地の更新→否定
抵当権設定後に借地(や借家)契約がなされても、それが短期のものであれば、抵当権者(や買受人)よりも優先とするのが短期賃貸借保護制度です。では、法定更新は適用されるのでしょうか。仮に適用されるとすれば更新が原則となり、これを賃貸人(買受人)が止めること(更新拒絶)はそう簡単に認められなくなります。
そもそも短期賃貸借保護制度は文字どおり、短期間に限って、本来劣後する賃貸借を保護する、という趣旨のものです。そこで、昭和38年最判は、差押がなされた後は法定更新にはならない、という解釈を採用しました。その後もこの解釈は定着しています。
なお正確には、法定更新を抵当権者や買受人に対抗できない、ということになります。差押前は(土地所有者と借地人の関係では)法定更新は適用されます。
昭和38年最判・差押後の借地の更新→否定
あ 判断
ところで、民法三九五条の短期賃貸借においても、一般的には、借地法借家法の適用を妨げるものではないが、抵当権実行による差押の効力が生じた後に右賃貸借の期間が満了したような場合には、借地法六条借家法二条の適用はなく、右賃貸借の更新を抵当権者に対抗できないと解するのが相当である。
い 理由
けだし、抵当権設定登記後に設定登記された賃貸借は、民法六〇二条の期間をこえないものにかぎり、例外として抵当権者に対抗しうることとし、かくして、抵当権の設定せられた不動産の利用と抵当権者の利益とを調整しようとする同法三九五条の趣旨にてらし、賃借権保護の限界として、右のように制限して適用すべきものと解するのが相当である。
※最判昭和38年8月27日
(2)昭和53年最判・差押後の借地の更新・建物買取請求→否定
昭和53年最判では、前記の昭和38年最判と同じように、差押後の法定更新を否定しました。
ところで、期間満了で法定更新にならない場合には借地人は本来建物買取請求をすることができます。
詳しくはこちら|借地期間満了時の建物買取請求権の基本(借地借家法13条)
結論として最高裁は建物買取請求も否定しました。形式的には、建物買取請求権は法定更新とセットになっているので、法定更新を対抗できないなら建物買取請求も否定、ということになります。ただ、昭和53年最判は実質的な理由として、これを認めると抵当権者(や買受人)の犠牲が大きすぎることからそこまで賃借権の保護を厚くしない、という利害のバランスを挙げています。
昭和53年最判・差押後の借地の更新・建物買取請求→否定
あ 結論→法定更新否定+建物買取請求否定
民法三九五条により抵当権者に対抗することができる土地の短期賃貸借の期間が抵当権実行による差押の効力を生じたのちに満了した場合には、賃借人は、借地法四条又は六条による期間の更新をもつて抵当権者に対抗することができないとともに(最高裁昭和三七年(オ)第二二二号同三八年八月二七日第三小法廷判決・民集一七巻六号八七一頁参照)、競落人に対し同法四条二項による地上建物等の買取請求をすることもまたできないと解するのが相当である。
い 理由
蓋し、抵当権者が更地を目的として抵当権の設定を受けた場合に、後日同地上に建築された地上建物につき土地の短期賃借権者が同条項による買取請求権を行使することができるとすると、地上に建物が建築されることにより土地の競落価格は低下を免れないが、抵当権設定に際して目的土地の上にどのような建物が建築されるかをあらかじめ想定することはことがらの性質上困難であるため、抵当権者は抵当権設定に際し目的土地の担保価値を適正に評価をすることができなくなり、ひいては取引の円滑な運用が阻害されることにもなること、さらに、競落価格の低下によつて抵当債権の完全な満足が得られなくなるような場合に、抵当権者に認められている民法三九五条但書による短期賃貸借の解除請求は、その訴訟による実現が必ずしも容易ではなく、実際上の機能を果たしているとはいいきれないことを考えあわせると、短期賃借権者の権利の保護は、同条本文によつて認められた期間内における土地の利用をもつて限度とし、それを超えて借地法四条二項による地上建物の買取請求権の行使にまで及ぼさないことが、抵当権と目的土地の利用権との適正な調和をはかることを目的とした民法三九五条の趣旨に合致するものと考えられるからである。
※最判昭和53年6月15日
7 関連テーマ
(1)賃貸借の短期と長期の判別が登場する他の状況(参考)
ところで、賃貸借の長期、短期の判別で、借地借家法の適用がどう影響するか、という問題は旧民法395条とは別の規定でも登場します。
処分権限を有しない者に関する民法602条、過半数の共有持分をもつ共有者に関する民法252条4項、強制管理の管理人に関する民事執行法95条、被保佐人に関する民法13条などです。
これらでは、別の解釈がとられるものもあります。別の記事で、横断的に比較しつつ説明しています。
詳しくはこちら|「管理」権限者による賃貸借・用益物権設定の範囲(共有者・各種管理人・被保佐人など横断的まとめ)
(2)短期賃貸借保護制度の悪用の歴史=廃止の経緯(概要)
前述のように、短期賃貸借保護制度は平成15年の民法改正で廃止されています。というのは、本来の想定どおりにこの制度が機能することはまれで、むしろ悪用の方が横行していたのです。よかれと思ってルールを作ったのに弊害しか起きなかった、という国の最高機関レベルの失敗例、黒歴史といえます。将来の立法に役立てるべきであることはもちろん、現在でも個別の案件で似たような妨害行為に注意を払う、予防策をとる上で役立つことはあります。
詳しくはこちら|短期賃貸借保護制度の悪用の歴史(=平成15年改正で廃止される経緯)
(3)現在の明渡猶予制度(概要)
前述のように、短期賃貸借保護制度は弊害が大きかったため、平成15年の民法改正で廃止されました。これに変わるものとして、同じ民法395条として、明渡猶予制度が作られています。賃借人を保護するものですが、改正前のように強すぎることがないように、つまり十分に保護は弱く設定されています。
詳しくはこちら|競売における明渡猶予制度(民法395条)
本記事では、平成15年改正前の短期賃貸借保護制度について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に土地や建物の賃貸借や競売に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。