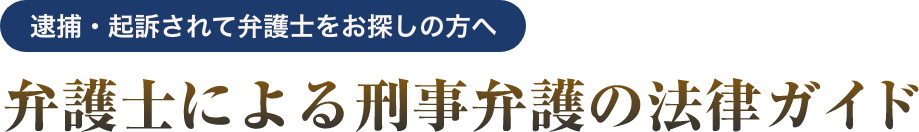【横領罪(刑法252条)における横領行為の全類型(解釈整理ノート)】
1 横領罪(刑法252条)における横領行為の全類型(解釈整理ノート)
横領罪の条文では、(犯罪)行為について「横領(した)」としか書かれていません。この点、実務では「不法領得の意思の発現行為」という解釈が一般的です。
詳しくはこちら|横領罪の基本(条文と占有・他人性の解釈・判断基準)
これだけだと、具体的にどのような行為が「横領」にあたるのかがはっきりしません。本記事では、多くの行為を類型的に整理して「横領」にあたるかどうか、という解釈を整理しました。
2 売却の「横領」該当性
(1)基本的な考え方
基本的な考え方
自己のために売却した場合、他に売却する旨の委託を受けて占有していた物件であっても、委託の趣旨に反したものとして横領罪が成立する
※大判昭和2年9月10日集6巻353頁
※最判昭和24年6月29日集3巻7号1135頁
※最決昭和41年9月6日第20巻7号759頁
(2)売却権限の解釈
売却権限の解釈
※広島高判昭和30年6月4日高集8巻4号585頁
(3)仮装売買の扱い
仮装売買の扱い
あ 原則的な考え方
譲渡担保に供した骨董品について、債権者の担保権実行を妨げるため仮装売買契約を締結した場合、物件を処分又は領得したとはいえず横領罪は成立しない
※大判昭和2年3月18日裁判例2刑27頁
い 仮装売買でも横領罪が成立する場合
仮装売買であっても、買主が対抗要件(仮登記を含む)まで備えるなど所有権侵害の危険を具体化させた場合には、不法領得の意思を実現させる行為として横領罪が成立する
(ア)船舶を仮装売買により引き渡した行為
※大判明治42年8月31日録15輯1097頁
(イ)虚偽の抵当権設定仮登記をした行為
※最決平成21年3月26日集63巻3号291頁
(4)売却意思表示と既遂時期
売却意思表示と既遂時期
売却の斡旋依頼行為も同様である
不動産については、登記の完了をもって既遂とする見解もあるが、個々の事案ごとに判断すべきである
※大判大正2年6月12日録19輯714頁
※大判昭和22年2月12日集26巻2頁
※東京高判昭和29年10月19日特報1巻9号396頁
3 二重売買の「横領」該当性
(1)判例の立場
判例の立場
あ 基本→横領罪成立
所有権を売却して対抗要件を経ないうちに同一物を別の者に売却する二重売買は横領罪に該当する
最初の譲渡で所有権は買主に移転し、売主は他人の所有物を占有していることになるため、これを他者に売却する行為は横領となる
い 判例
ア 動産
※名古屋高判昭和29年2月25日特報33号72頁
イ 不動産
※大判明治44年2月3日録17輯32頁
※最判昭和30年12月26日集9巻14号3053頁
※最判昭和31年6月26日集10巻6号874頁
※最判昭和33年10月8日集12巻14号3237頁
※最判昭和34年3月13日集13巻3号310頁
(2)学説の見解
学説の見解
(代金支払等が行われていない時点では買主が刑法上処罰に値する程度の所有権の実質を備えていないため)
(3)第2売買における登記と既遂時期
第2売買における登記と既遂時期
二重売買の場合、第2買主に対して所有権移転登記を経るか、これに準じる行為に及んだ段階で不法領得の意思が外部的に発現したと認めるのが相当である
(4)第2買主に対する詐欺罪(参考)
第2買主に対する詐欺罪(参考)
※東京高判昭和48年11月20日高集26巻5号548頁
二重譲渡の刑事責任については、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|2重譲渡や2重抵当による刑事責任(横領罪・背任罪の成立)
4 贈与の「横領」該当性
贈与の「横領」該当性
あ 基本
委託の趣旨に反して不法領得の意思をもって委託物を他人に贈与することは横領行為に該当する
い 裁判例
会社の自社株式を保管する代表取締役社長が、幹部役職員に自社株を配分贈与する旨の意思表示をし、各配分取得者との合意によりその者のために株式を占有するに至ったときに横領罪が成立する
※東京高判昭和39年4月8日東時15巻4号47頁
5 交換の「横領」該当性
交換の「横領」該当性
あ 基本
権限なくして委託物を他の物と交換することも横領行為に該当する
い 判例
(ア)特定物として寄託された10円紙幣1枚を5円紙幣1枚と取り換えた場合
※大判明治43年9月27日録16輯1556頁
(イ)食料営団出張所長として保管していた小麦を権限なく醤油及び現金と交換して譲渡した場合
※最判昭和26年5月31日裁判集(刑事)46号663頁
6 担保供用の「横領」該当性
(1)質権の設定
質権の設定
質権設定自体が横領行為に当たるため、質権実行の有無や受戻し意思の有無は問わない
譲渡担保設定権者が譲渡担保目的物を入質した場合、所有権は債権者に移転しているため、入質行為は横領となる
転質(質物の再担保)については、債務者の承諾なく行った場合、当初の質権の範囲を超えない限度では横領罪とならないが、債権額、存続期間等が質権設定者に不利な結果を生ずる場合は横領罪が成立する
※大連決大正14年7月14日
※最決昭和45年3月27日(商品仲買人の証券転質)
(2)抵当権・譲渡担保権の設定
抵当権・譲渡担保権の設定
あ 委託された財産
委託された他人所有物への抵当権設定、譲渡担保権設定は横領罪となる
※大判明治43年10月25日(抵当権設定)
※大判大正6年6月25日(抵当権設定)
※大判昭和9年7月19日(譲渡担保権設定)
い 譲渡済の不動産
他人に譲渡した不動産の所有権移転登記前に抵当権を設定し登記すれば横領罪となる
※最判昭和31年6月26日
※最判昭和34年3月13日
(3)既遂時期
既遂時期
あ 質権
質権については、担保に供する意思表示をしたことにより横領罪が成立する
※大判大正11年2月23日(宿泊費担保として委託物を差し置いた事案)
い 抵当権
抵当権については見解が分かれる
仮登記であっても横領罪が成立するとの判例がある
※最決平成21年3月26日(虚偽表示による抵当権設定)
7 債務の弁済への充当の「横領」該当性
債務の弁済への充当
あ 基本
金銭等の委託物を自己の債務弁済に充当することは横領罪に当たる
※大判昭和9年12月15日
※最決昭和32年12月19日
い 裁判例
手形取立て依頼を受け、自己名義の銀行預金口座に振り込まれた手形金を、自己が当該銀行に対して有する債務の弁済に充当した場合は横領となる
※東京高判昭和59年11月6日
8 預金及びその引出し・振替の「横領」該当性
(1)預金行為
預金行為
あ 基本
受託者が遅滞なく委託者に引き渡すべき委託金を自己名義で預金した場合、特段の事情がない限り横領となる
※東京高判昭和31年2月25日
い 本人のため→不法領得の意思を否定
ただし、もっぱら委託者本人のためになされたと認められる場合は不法領得の意思を欠く
納金ストの事案で一時保管の意味で形式上自己名義の預金としたにすぎないときは横領罪が成立しない
※最判昭和33年9月19日
※最判昭和31年9月19日
(2)預金の引出し
預金の引出し
あ 基本
委託の趣旨に反して預金を引き出す行為は横領罪となる
※大判大正元年10月8日
※大判大正8年9月13日
※東京高判昭和59年11月6日
い 事例
他人に交付するために預かった保証金を委託者の了解を得て一時保管の方法として自己名義で預金していたが、委託者に無断で払戻しを受けて自己の用途に費消する行為について、不正に領得する意思を生じたのが払戻しの前後であるかを問わず横領となる
※大判大正9年3月12日
(3)預金の振替
預金の振替
9 小切手の振出し・換金の「横領」該当性
(1)小切手の振出し・換金
小切手の振出し・換金
(2)背任罪とする判例
背任罪とする判例
あ 銀行支店長代理
銀行支店長代理が小切手を作成し、後に交付して割引かせた事案
※大判昭和8年12月18日
い 農協組合長
農協組合長が自己の権限に基づいて組合長名義の小切手を振り出す行為は、自己の占有する他人の物を横領したものではなく、任務に背いて農協組合に財産上の損害を与えたものとして背任罪を構成する
※広島高判昭和27年8月4日
う 資金を預かった者
他人の金銭を自己名義の当座預金に預け入れていた者が、小切手を振り出して他人に交付したにとどまり、銀行から金銭を引き出すに至らないときは、横領罪には当たらない
※大判昭和7年7月11日
(3)横領罪とする判例
横領罪とする判例
あ 農協理事
農協理事が組合の小切手を貸与し、返済金等を着服した事案において、小切手の貸与自体が横領行為である
※東京高判昭和34年12月8日
い 振出担当者の上司
部下に小切手を作成させ、実際には決済すべき債権債務関係のない会社の者に交付させた上で、受け取って現金化した事案において、預金払出しの段階において横領罪を構成する
※東京高判昭和51年7月13日
う 会社役員
会社取締役総務部長が私的用途に充てるために小切手を振り出して換金した事案において、当該換金行為をもって横領とする
※広島高判昭和56年6月15日
10 貸与の「横領」該当性
(1)基本原則
基本原則
賃貸借、消費貸借、使用貸借のいずれであるかにかかわらない
貸与が貸付名義で行われたにすぎないのか真実のものかに関係なく横領行為となる
※大判昭和6年7月2日
(2)賃借物の転貸
賃借物の転貸
あ 民法上の扱い(前提)
賃借物を賃貸人に無断で転貸することは民法上は許されない(民法612条1項)
い 刑法上の扱いについての見解
一定の限度で社会的に容認されている相当行為として横領に当たらないという見解がある
認められた物の利用の範囲内で転貸するごときは無権限の行為とはいえず、所有者の権利を物権的に害しないとする
11 金融機関の役職員による不当貸付の「横領」該当性
金融機関の役職員による不当貸付の「横領」該当性
あ 横領罪となる場合
役職者自身の名義・計算によって貸し付けたとき
い 背任罪となる場合
金融機関の名義・計算で貸付が行われたとき
12 会社財産の支出の「横領」該当性
(1)会社の目的の範囲内での支出
会社の目的の範囲内での支出
あ 基本
会社役員が、保管する会社財産を会社の目的の範囲内で会社のために支出する行為は、業務上横領罪や特別背任罪に該当しない(会社法960条)
い 事案
定款の目的に「証券投資」が記載されている株式会社において、社長が会社所有の現金及び株券を取引保証金に使用して株式の信用取引を行った結果負債を生じ、これを補填するために会社所有の現金及び株券等を証券会社に交付した場合、信用取引も会社目的の証券投資に含まれるものであり、社長の行為は会社の利益を図る目的に出た業務上の活動であって、業務上横領罪の犯意を欠く
※大阪地判昭和33年5月15日
(2)会社の経営や業務と無関連な支出
会社の経営や業務と無関連な支出
あ 基本
会社等の役員が、その経営や業務等と何ら関連のない事項につき自己のためにする趣旨で、管理している会社財産を支出するときは業務上横領罪を構成する
い 裁判例
ア 学校法人の理事長
学校法人である学園の理事長が、個人の資産としてハワイの不動産を購入するため学園の金員を海外送金した場合
※東京地判平成9年3月17日
イ 会社社長
出版社の社長がコカイン等の薬物を購入する目的でその保管する会社資金を海外に送金した場合
※千葉地判平成8年6月12日
(3)地位保全目的での支出
地位保全目的での支出
(4)違法行為のための支出(判例)
違法行為のための支出(判例)
あ 事案
株式会社の取締役経理部長及び経理部次長が、自社の株式を買い占めた仕手集団に対抗する目的で、第三者に対し、その買占めを妨害するための裏工作を依頼した上、同社のため保管していた現金をその工作資金及び報酬等に充てるために支出した
あ 裁判所の判断
当該行為ないしその目的とするところが違法であるなどの理由から委託者たる会社として行い得ないものであることは、行為者の不法領得の意思を推認させる1つの事情とはなり得る
しかし、行為の客観的性質の問題と行為者の主観の問題は、本来、別異のものであって、たとえ商法その他の法令に違反する行為であっても、行為者の主観において、それを専ら会社のためにするとの意識の下に行うことは、あり得ないことではない
したがって、その行為が商法その他の法令に違反するという一事から、直ちに行為者の不法領得の意思を認めることはできない
※最決平成13年11月5日
13 共有物の占有者による独占の「横領」該当性
(1)共有物の排他的占有
共有物の排他的占有
※大判大正8年3月31日
(2)共有金銭の無断費消
共有金銭の無断費消
※大判明治44年2月9日
※大判昭和10年8月29日
※最決昭和43年5月23日
14 交付の「横領」該当性
(1)基本的規範
基本的規範
(2)判例の立場
判例の立場
あ 共犯者への引渡し
共犯者の一人が管理する他人の物件を不正に領得する意思で他の共犯者に引き渡した場合は、その引渡しが売買、贈与、交換等の権利移転の法律上の名義によるものであるか否かにかかわらず横領罪となる
※大判大正4年4月24日
※大判大正6年7月14日
※大判昭和8年4月11日
※大判昭和8年5月2日
い 債務弁済への充当
手形の割引を委託されて手形の交付を受けた割引周旋人が、委託者の明示又は黙示の許諾がないにもかかわらず、その手形を自己の債務の弁済に充当する目的で他に裏書交付することは横領罪に当たる
※東京高判昭和27年10月31日(特報37号78頁)
う 恐喝者への交付
恐喝を受けて他人の財物を交付したときにも横領罪が成立するが、委託物を恐喝者に交付しようとすれば相手が現実にこれを受領しなくとも横領罪は既遂となる
※大判昭和6年3月18日(集10巻109頁)
15 拐帯(持ち逃げ)の「横領」該当性
(1)基本的規範
基本的規範
※東京高判昭和34年3月16日(高集12巻2号201頁)
(2)判例の立場
判例の立場
※東京高判昭和34年3月16日(高集12巻2号201頁)
(3)学説上の議論
学説上の議論
あ 横領既遂時期に関する見解
持ち逃げする意図で集金金銭を携帯して街を歩いている事実のみでは横領罪の成立を認めることは困難であり、他所に高飛びするために駅に赴いて切符を購入してホームに行くなど集金金銭を会社に納付しない意思が明確に認められるときにはじめて不法領得の意思の発現と認められる外部的行為があったとみるべきとする見解がある
い 認定基準に関する議論
後戻りの余地が確定的に失われたときに、拐帯横領が既遂に達するとみるべきという基準については、他の類型の横領行為の内容と比較してやや厳しい表現の感があるとの指摘もある
16 抑留(返還拒絶)の「横領」該当性
(1)基本的規範
基本的規範
委託者から返還を求められたにもかかわらず、これに応じない場合には横領となる
※大判明治44年5月22日(録17輯897頁)
※大判大正4年2月10日(録21輯94頁)
(2)自己の権利主張による抑留
自己の権利主張による抑留
あ 所有権の主張
他人の物の占有者が、受託物を自己の所有物であると主張して争う場合は横領となる
※大判大正5年8月8日(録22輯1310頁)
い 民事訴訟の提起による横領
ア 基本
自己の所有物であると主張して民事訴訟を提起したり応訴したりする場合も横領となる
イ 所有権確認・登記抹消請求訴訟
登記名義を預けられていた者が、家屋を自分の所有物であると主張して所有権確認及び登記抹消請求の民事訴訟を提起したもの
※大判昭和8年10月19日(集12巻1828頁)
ウ 所有権移転登記請求訴訟
他人の建物を管理占有していた者が偽造文書を利用して建物所有者に対し自己の所有権を主張し、所有権移転登記を求める旨の民事訴訟を提起したもの
※最判昭和25年9月22日(集4巻9号1757頁)
ウ 所有権移転登記請求に対する応訴
登記簿上自己が所有名義人となって預かり保管中の不動産につき、所有者からの所有権移転登記請求の訴え提起に対し応訴して自己の所有権を主張し抗争したもの
※最決昭和35年12月27日(集14巻14号2229頁)
(3)虚偽の申述による横領
虚偽の申述による横領
あ 基本的な事例
銀行員から他人に渡すべき現金を誤って受け取った者が、その銀行員から受け取りすぎていないか質問されたのに対し、そのような事実はないと答えた
※大判明治43年12月2日(録16輯2129頁)
余剰を返還する前提で県から現物支給されていたセメントを保管していた者が土木事務所の職員にセメントは残存しないと虚偽の申述をした場合
※高松高判昭和36年9月13日(高集14巻7号479頁)
い 特殊な事例
占有中の部落所有の金員について、会合の場において、個人として組合から特別慰労金としてもらい受けたもので部落に差し出すものではないと主張した場合
※大判昭和5年3月1日(新聞3122号13頁)
念仏講の講員の共有物として保管していた仏具を次の当番の者に引き継ぐ際に、引継ぎを受けたものと偽って異なる物を引き渡した場合
※大阪高判昭和26年6月11日(高集4巻5号550頁)
(4)不作為による抑留
不作為による抑留
あ 基本
特に委託の趣旨から行わなければならない行為がある場合には、そのような行為をしないまま占有を続けることで不法領得の意思を実現したと解し得ることがある
い 判例
司法警察官が被疑者から任意提出を受けた腕時計や現金について、領選の手続をなさず、かつ、検事局に送致しなかった場合
※大判昭和10年3月25日(集14巻325頁)
銃砲等所持禁止令による保管許可申請手続をすることを頼まれて受け取った脇差と太刀を保管中、所定期日までに手続をせず、以後自己のためにそのまま蔵置した場合
※最判昭和27年10月17日(裁判集(刑事)68号361頁)
い 返還期限の徒過
ア 裁判例
所有者に交付すべき期日を過ぎたような場合には、その時点で横領行為があったと認められるもの
※仙台高判昭和28年10月19日(特報35号65頁)
昼頃までに返す趣旨で午前9時頃に自動車を借り受けた者が、その許諾の限度を超えて警察官に逮捕されるまでの8日間にわたり自動車を乗り回したような場合には横領罪が成立する
※大阪高判昭和46年11月26日(高集24巻4号741頁)
イ 別の見解
期限が来ても返還しないで抑留するような単なる不作為は横領とは認め難いとの見解もある
(5)抑留による横領の既遂時期
抑留による横領の既遂時期
あ 権利主張後の撤回
権利者である旨主張したり抗争したりして、不法領得の意思を実現する行為が行われれば横領罪は既遂に達して成立するので、その後に訴えを取り下げても未遂にとどまることにはならない
※最判昭和25年9月22日(集4巻9号1757頁)
い 履行期前の横領と事後の返還
県から現物支給され、余剰を返還することとされていたセメントを保管していた者が不法領得の意思をもって土木事務所の職員にセメントは残存しないと虚偽の申述をしたことで横領罪は既遂になるので、それが返還債務の履行期到来前であったことや、履行期到来前に不正が発覚してセメントを返還したことは犯罪の成否に消長を及ぼさない
※高松高判昭和36年9月13日(高集14巻7号479頁)
17 搬出・帯出の「横領」該当性
(1)基本的規範
基本的規範
(2)判例の立場
判例の立場
あ 売却目的の搬出
他人所有の郵便切手を占有する者が、自己のために売却するためそれを自宅から搬出した以上、その後に郵便切手が売却されたかどうかは犯罪の成否に影響しない
※大判明治43年10月11日(新聞677号18頁)
い 期限前の帯出
郵便局職員が、同僚職員の俸給中から分類所得税として源泉徴収して保管する金員を自宅に持ち帰ることによって横領罪は既遂となり、税金を政府に納入する期限の前であっても犯罪の成否に影響しない
※東京高判昭和34年4月21日(東時10巻4号257頁)
(3)各種の搬出・帯出事例
各種の搬出・帯出事例
あ 公文書等の帯出
市の助役が共犯者をして自己の保管する公文書を市役所以外に帯出して隠匿させた場合
※大判大正2年12月16日(録19輯1440頁)
収入役が保管中の村役場の基本財産である債券を役場より持ち出した場合
※大判昭和10年7月4日(集14巻753頁)
い 有価証券等の帯出
信用組合連合会の主事が有価証券類を保管金庫から取り出して株式清算取引の証拠金代用又は債務の担保として差し入れた場合
※大判昭和10年7月10日(集14巻799頁)
う 仮処分物件の搬出
執行吏により仮処分を受けた物に関し代理占有保管の委任を受けた者が、これを売却する意思で指定された場所から搬出して他の場所の倉庫に預け入れた場合
※最決昭和36年12月26日(集15巻12号2046頁)
え 麻薬の持出し
麻薬施用者の地位を有する診療所長である医師が、診療所の金庫で保管していた麻薬を自己又は妻の麻薬中毒症緩和に施用するために持ち出して自宅に持ち帰った場合
※東京高判昭和26年11月20日(高集4巻13号1916頁)
(4)機密資料等の持出し
機密資料等の持出し
あ 売却目的の持出し
保管する会社所有の資料を他に売却することが横領になる
※神戸地判昭和56年3月27日(判時1012号35頁)
い コピー目的の持出し
機密資料の内容をコピーするために保管場所から持ち出した場合には、その持出し行為が横領となる
※東京地判昭和60年2月13日(刑裁月報17巻12号22頁)
※東京地判平成10年7月7日(判時1683号160頁)
18 費消の「横領」該当性
(1)費消の定義
費消の定義
※大判明42年6月10日録15輯759頁
(2)金銭の費消
金銭の費消
19 着服の「横領」該当性
着服の「横領」該当性
あ 着服の定義
着服とは、他人のための委託物の占有を自己のための占有に切り替えることをいう
い 着服の性質
揚帯や抑留と並んで費消等の何らかの処分行為に至る前段階で不法領得の意思を発現したと認められる場合を包含する幅広い概念であり、その後の費消等の事実が証拠上は具体的に判明しない場合、少なくとも着服したことについては認定し得ることもある
※東京高判昭30年3月14日裁特2巻6号153頁(特定されていない複数の費消行為ではなく、その前段階の一回の着服行為を横領と認める)
※大判大7年6月28日録24輯815頁
う 訴訟法上の問題
着服行為の内容を適示する必要があり得る
20 隠匿の「横領」該当性
(1)隠匿横領が認められた事例
隠匿横領が認められた事例
※大判明44年6月8日録17輯1113頁
イ 学校工事設計図面 市の助役が不正工事の発覚をおそれ、自己の保管している市立小学校の工事設計図面を、共犯者をして市役所以外に帯出させ隠匿させた事案
※大判大2年12月16日録19輯1440頁
ウ 金銭 他人の金銭を占有する者が不正に領得する意思でこれを自宅内に隠匿した事案
※大判大8年6月7日新聞1582号20頁
エ 米穀 県農業会支部出張所主任が自己のために処分する意図で自己の管理する倉庫に保管する米穀を同倉庫内の他の場所や他の倉庫に移して隠匿した事案
※大判昭21年10月18日集25巻42頁
オ 現金 経営危機に陥った会社の代表取締役が、会社の資産である現金15億2000万円につき、一部は自己や第三者のためにのみ使用し、その余はその後の事態の推移に応じて自己又は会社のために使おうとの意図で、母や親密な関係の女性らに依頼して隠匿した事案
※東京高判昭56・12・24高集34巻4号461頁
(2)隠匿と不法領得の意思
隠匿と不法領得の意思
21 毀棄の「横領」該当性
毀棄の「横領」該当性
22 参考情報
参考情報
本記事では、横領罪における横領行為の全類型について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に横領罪に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。