【和解契約の効力(錯誤・詐欺・強迫による取消)の理論と実務】
1 和解契約の効力(錯誤・詐欺・強迫による取消)の理論と実務
トラブルが起きた時に、交渉の末、「和解」が成立して終了(解決)する、という局面はありふれています。しかし、中には、実は解決していなかった、後から別の事情が発覚した、ということがあります。ここで「和解契約」というものの効力が問題となります。本記事では、和解契約の効力について実務的観点から説明します。
2 和解契約の基礎理論(参考)
和解契約の法的性質は、諾成・有償・双務契約です。有効に成立するためには、①当事者間に紛争が存在していること、②当事者双方による相互の譲歩(互譲性)があること、③紛争を終結させることの合意があること、という要件を満たす必要があります。
互譲性とは、単に一方の主張が全面的に受け入れられるのではなく、双方が何らかの利益を手放すことで合意に至ることを意味します。ただし、実務上は当事者の一方が全く譲歩しない条件で示談することもあり得ます。そのような場合は、典型契約としての「和解契約」ではありませんが、和解契約類似の非典型契約として、和解契約と同様に法的な効力を持ちます(有効です)。
3 裁判外の和解と裁判上の和解の効力の違い
(1)裁判外の和解の効力と限界
裁判外の和解は、裁判所の関与なしに、当事者間で直接締結される和解契約です。当事者間の合意によって成立し、その合意内容は契約として法的な拘束力を持ちます。しかし、原則として直接的な強制執行力はありません。相手方が和解内容を履行しない場合に強制執行をしようと思ったら、その和解契約に基づいて改めて訴訟を提起する必要があります。
ただし、金銭の支払いを内容とする裁判外の和解契約を強制執行認諾文言付き公正証書として作成することで、相手方が支払いを怠った場合に訴訟を経ることなく強制執行が可能となります。
詳しくはこちら|公正証書の効力・作成手続(情報整理ノート)
(2)裁判上の和解の特別な効力
裁判上の和解(訴訟上の和解や即決和解)が成立すると、その合意内容は和解調書に記録され、確定判決と同一の効力を持ちます。具体的には、①訴訟終了効、②執行力、③確定効という三つの効力が認められます。つまり、差押などの強制執行をすることができます。
詳しくはこちら|債務名義の種類は確定判決・和解調書・公正証書(執行証書)などがある
4 和解契約の紛争終結効(確定効)
和解契約の重要な効果として「紛争終結効」があります。これは、和解によって解決した紛争について、当事者が後日改めて争うことができなくなる効果です。
ただし、和解の後に「前提として事情が間違っていた」などの特殊事情がある場合には、例外扱いとなることもあります。典型例は、損害賠償の和解をした後に後遺症が発覚したケースで追加の請求が認められるようなケースです(昭和43年最判)。
詳しくはこちら|和解契約の効力(確定効の範囲・錯誤主張の可否)(民法696条)(解釈整理ノート)
5 和解契約の効力を争う法的根拠
(1)錯誤による和解契約の効力への影響
一般に、和解の対象となった事項そのものについての錯誤(勘違いがあったので取り消すこと)は原則として認められません(最判昭和36年)。
しかし、和解の前提として当事者が争わなかった事実について錯誤があった場合には、和解の効力が否定されることがあります。有名な実例として、ジャムの代金支払いの和解後にジャムが粗悪品であることが判明したケースで、ジャムの品質は争いの目的ではなく和解の前提であったとして、錯誤による和解の無効を認めたものがあります(昭和33年最判)。
詳しくはこちら|和解契約の効力(確定効の範囲・錯誤主張の可否)(民法696条)(解釈整理ノート)
(2)その他の無効・取消事由
詐欺や強迫によって和解契約が締結された場合、その和解契約は取り消すことができます。また、和解契約の内容が公序良俗に反する場合や強行法規に違反する場合には、その和解契約は無効となります。
(3)裁判上の和解の無効
以上のように和解も無効となることがある、というのは裁判上の和解でも理論的には同じです。ただし、裁判官が関与してい和解が成立しているので、「勘違いだった」ということ(錯誤などによる取消)が認められる可能性は低いです。
詳しくはこちら|訴訟上の和解が無効となった実例(裁判例)
また、裁判上の和解が無効だ、と主張するには、期日指定申立などの裁判所の手続が必要になります。
詳しくはこちら|訴訟上の和解の無効を主張する手続(期日指定申立など)
6 和解契約書の清算条項の効力
清算条項とは、和解契約に定めるもののほか、当事者間には一切の債権債務が存在しないことを相互に確認する条項です。清算条項の効力によって、和解の対象となった紛争については、原則として後日改めて請求を行うことはできなくなります。
ただし、前述した理論により、和解当時に予見できなかった損害については、清算条項の効力が及ばないとされる場合もあります。
7 これから和解をする場合の実務的注意点
裁判外の和解契約は、原則として直接的な強制執行力を持ちません。そのため、強制執行認諾文言付き公正証書の作成や裁判上の和解の活用を検討すると良いでしょう。
また、和解契約の効力を強化するためには、条項の設計が非常に重要です。紛争の背景や経緯、各当事者の義務内容、履行方法や期限、義務不履行時のペナルティなどを具体的かつ明確に記載することが望ましいです。
さらに、和解契約の効力が後日争われるリスクを減らすためには、錯誤のリスクを減らす情報開示、詐欺や強迫のリスクを減らす公平な交渉環境の確保、公序良俗違反や強行法規違反のリスクを減らす法令適合性の確認などの対策が有効です。
8 まとめ
和解契約は、適切に活用することで、紛争を迅速かつ効果的に解決し、当事者双方にとって満足のいく結果をもたらす可能性があります。しかし同時に、その効力は絶対的なものではなく、特定の条件下では後日争われる可能性もあります。
和解契約の効力を最大化するためには、和解の内容と、和解の方法(公正証書などの選択肢)をしっかり検討し、最適な選択をすることが重要です。
本記事では、和解契約の効力の理論と実務について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に和解の効力に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
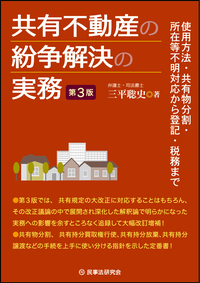
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!





