【和解契約の効力(確定効の範囲・錯誤主張の可否)(民法696条)(解釈整理ノート)】
1 和解契約の効力(確定効の範囲・錯誤主張の可否)(民法696条)(解釈整理ノート)
和解(契約)をすると、常識的に紛争が終わります。しかし、後からまだ問題が残っているということが判明することもあります。事情によっては、和解の効力が及ばない、つまり追加の請求が認められることもあります。本記事では、このような和解契約の効力について、条文規定やその解釈(判例)を整理しました。
なお、和解契約の効力について、実務面を含めた全体像は別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|和解契約の効力(錯誤・詐欺・強迫による取消)の理論と実務
2 民法696条の条文と趣旨(確定効)
(1)民法696条の条文
民法696条の条文
第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
※民法696条
(2)立法目的(趣旨)→確定効
立法目的(趣旨)→確定効
あ 確定効
民法696条の立法目的は、和解の安定性を確保することにある
和解をした以上、原則として争いの蒸し返しは許されないという確定効を確保するものである
い 和解の確定効の根拠
(ア)錯誤無効の主張自体が和解の趣旨に反する(イ)和解の安定性確保のため、和解の趣旨がどうであれ錯誤無効の主張を封じる
3 確定効の範囲
(1)確定効の範囲の基本→当事者・争点
確定効の範囲の基本→当事者・争点
確定効が及ぶ権利関係は、争点について取り決めた事項に限られる
(2)確定効を認めた(錯誤を否定した)具体例(判例)
確定効を認めた(錯誤を否定した)具体例(判例)
あ 昭和28年最判
賃貸人から自己使用の必要を理由に明渡の調停を申し立てられた賃借人との間で合意解除の調停が成立した後、賃貸人の自己使用の必要がなかったことが判明したケース
※最判昭和28年5月7日民集7・5・510
い 昭和36年最判
期間満了により借地権が消滅したか否かが争われ、満了の日から2年後に土地を明け渡す旨の民事調停が成立したが、当時、借地人は法定更新の制度を知らなかったケース
※最判昭和36年5月26日民集15・5・1336
う 昭和38年最判
手形金の支払を訴求された振出人が手形債務の支払方法に関し訴訟上の和解をしたが、当時、振出人は満期後の譲受人を満期前に譲り受けた善意者と誤信していたケース
※最判昭和38年2月12日民集17・1・171
4 和解の有効要件
和解の有効要件
あ 有効要件→処分の能力+権限
和解は係争権利関係の処分を目的とする契約であるため、有効に成立するためには処分の能力・権限が必要である
い 処分できない権利に関する和解(無効)の例
ア 権利能力ない胎児
電車事故による損害賠償につき、権利能力のない胎児を代理して和解をしても、その効力は出生した子に及ばず、その子は損害賠償を求めることができる
※大判昭和7年10月6日民集11・2023
イ 認知請求権の放棄
婚外子の父に対する認知請求権は放棄することができないため、婚外子が和解により父から財産をもらって認知請求権を放棄しても、認知の訴えを提起できる
※最判昭和37年4月10日民集16・4・693
5 確定効の範囲外の錯誤
(1)確定効の範囲外→錯誤の適用あり
確定効の範囲外→錯誤の適用あり
(2)前提とする転付命令の無効→錯誤適用あり
前提とする転付命令の無効→錯誤適用あり
※大判大正6年9月18日民録23・1342
(3)「勝敗未定」の前提が誤っていた→錯誤適用あり
「勝敗未定」の前提が誤っていた→錯誤適用あり
※大判大正10年10月3日民録24・1852
(4)「転貸承諾あり」の前提が誤っていた→錯誤適用あり
「転貸承諾あり」の前提が誤っていた→錯誤適用あり
※大判昭和9年7月25日新聞3728・12
(5)ジャムのクオリティの誤解→錯誤適用あり
ジャムのクオリティの誤解→錯誤適用あり
※最判昭和33年6月14日民集12・9・1492
6 和解の効力の性質論
(1)和解の効力の性質→認定的効力と付与的効力
和解の効力の性質→認定的効力と付与的効力
あ 認定的効力と付与的効力の基本
認定的効力とは旧権利関係を確認するものであり、付与的効力とは新たに権利関係を創設するものである
い 具体例
ア 付与的効力の例
不動産所有権の帰属が争われ、和解でY所有と決めた後でX所有を裏付ける証拠が発見された場合、所有権はXからYに「移転」したものとなる
イ 認定的効力の例
Xが100万円の代金債権を有するか争われ、和解で50万円の債権と決めた後で100万円の債権を裏付ける証拠が発見された場合、50万円は和解により「消滅」したことになる
(和解内容の50万円は債権を認定(確認)したことになる)
(2)判例における認定的・付与的効力の判定
判例における認定的・付与的効力の判定
あ 賠償に関する和解後の求償問題
不法行為の成否まで争った和解は付与的効力があり、賠償額のみの和解は認定的効力しかない
※大判大5年5月13日民録22・948
い 消費貸借上の債権と和解
弁済方法変更のみの和解では債権は消滅しない
※大判大9年6月5日新聞1742・17
う 詐害行為取消と和解
貸金請求事件の和解が認定的か創設的かにより、先立つ不動産売却の詐害行為性が左右される
※大判昭和2年10月27日新聞2775・14
え 時効の適用と和解
不法行為に基づく損害賠償請求権に関する和解後も、3年の消滅時効(民法724条)が適用される
※大判昭和7年9月30日民集11・1868
お 賃貸借契約解除の無効と和解
解除が有効であっても、これを無効とした和解は創設的効力を生じ、賃貸借は存続する
※大判昭和15年7月13日新聞4604・11
か 手形金請求訴訟と和解
手形債務の存否に関する和解は創設的効力があり、履行方法のみの和解は認定的効力がある
※大判昭和15年10月8日法学10・324
7 賃貸借に関する和解の問題
(1)一時使用目的の判定
一時使用目的の判定
あ 基本(一時使用目的に関する紛争)
訴訟上の和解や民事調停で成立した土地賃貸借が一時使用目的にあたるかどうかが争われるケースは多い
い 一時使用を肯定した判例
ア 7年間の借地
買主が自己利用の必要性から借地人と7年間の賃貸借として調停成立した場合は一時使用と解される
※最判昭和32年11月25日民集11・12・1978
イ 8年間の借地
仮設建物所有の目的での賃貸借後、無断で本建築した賃借人との調停で8年弱の期間設定と建物贈与の合意があった場合も一時使用と解される
※最判昭和33年11月27日民集12・15・3300
ウ 10年間の借地
不法占拠を理由とする土地明渡訴訟中に約10年間の賃貸借と期間満了時の建物収去・土地明渡の和解が成立した場合も一時使用と解される
※最判昭和43年3月28日民集22・3・692
う 一時使用を否定した判例(20年間)
料理店経営者が建物所有目的で20年間の土地賃貸借を訴訟上の和解で成立させた場合、この期間は借地法の存続期間に適するような長期であるため一時使用とはいえない
※最判昭和45年7月21日民集24・7・1091
借地の「一時使用目的」の判断がなされた具体的ケースについては、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|借地の「一時使用目的」を判断した判例(集約)
(2)期限付き合意解除(建物)→有効
期限付き合意解除(建物)→有効
※最判昭和27年12月25日民集6・12・1271
※最判昭和28年5月7日民集7・5・510
期限付き合意解除の効力については、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|建物賃貸借における期限付合意解除(合意解除+明渡猶予)の有効性
8 和解後の後遺症→想定外であれば追加請求可能
和解後の後遺症→想定外であれば追加請求可能
※最判昭和43年3月15日民集22・3・587
9 関連テーマ
(1)訴訟上の和解が無効となった実例(裁判例)
10 参考情報
参考情報
本記事では、和解契約の効力について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に過去に成立した和解(合意)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
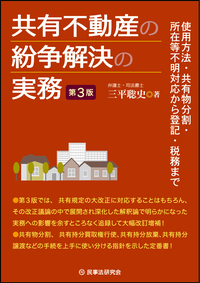
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!





