【督促・催告・相当期間に関する問題の整理】
1 督促・催告・相当期間のまぎらわしさ
いろいろな場面で、督促や催告が要件の1つとなっていることがあります。つまり督促や催告で一定の法律的な効果が発生するというものです。
督促や催告では『相当の期間』が必要とされることがあります。
督促・催告・相当期間が要件などとして、法律の適用の場面で登場することは多いのです。
用語が同じで概念・解釈が似ているので、誤解しやすいです。
そこで、本記事では、督促・催告・相当期間が登場する法律の規定や解釈をまとめておきます。
2 督促・催告・相当期間に関する問題の整理
督促・催告や相当期間が登場する法律の規定や解釈について、まずは項目だけを並べてみます。
督促・催告・相当期間に関する問題の整理
3 履行遅滞による解除の督促と相当期間
履行遅滞による解除において『相当期間を定めた督促』という要件があります。この内容を整理します。
履行遅滞による解除の督促と相当期間(※1)
4 期限の定めのない債務の付遅滞の履行請求
期限の定めのない債務は、履行請求によって履行遅滞に陥ります。これは債務一般についての規定です。どのような契約によって生じた債務であるかは問題になりません。
期限の定めのない債務の付遅滞の履行請求(概要)(※2)
履行遅滞に陥らせるための要件として
履行の請求(催告)がある
相当の期間は不要である
※民法412条3項
民法412条の解釈については別の記事で整理してあります。
詳しくはこちら|履行期と履行遅滞・催告(民法412条)(解釈整理ノート)
5 消費貸借の催告と期間
返還時期の定めのない消費貸借については、単純に履行請求だけで履行遅滞に陥るわけではありません。消費貸借については(上記※2)の規定の例外、つまり特別規定があるのです。
消費貸借の催告と期間(※3)
→『相当の期間を定めた返還の催告』により返還を請求できる
大雑把な目安=7日程度(以上)
※民法591条
詳しくはこちら|返還時期の定めのない貸金は『相当期間』の催告が必要
6 期限の利益喪失のための催告の期間
督促の結果、期限の利益喪失となることもあります。これは上記の規定・解釈と異なり、法律上の規定が根拠ではありません。
期限の利益喪失のための催告の期間(※4)
あ 基本事項
特約による期限の利益喪失事由として
催告や督促が約定されている場合
→『催告+相当期間の経過』が期限の利益喪失の要件となる
い 解釈の枠組み
特約の内容の解釈である
条文の解釈ではない
→明確な基準(判例)がない
履行遅滞による解除(民法541条)の解釈に準じる傾向がある
う 公的な目安
7日あれば期間として確実であるという見解がある
必須の日数という趣旨ではない
司法研修所でまとめた目安である
※東京簡裁の支払督促の運用;平成28年12月受付窓口ヒアリング
7 使用貸借の相当期間(参考)
『相当期間』が登場する民法上の規定として使用貸借があります。前記の催告における相当期間とは本質的に異なるものです。ただし、用語が同じなので、誤解が生じることもあるようです。そこで参考として挙げておきます。
使用貸借の相当期間(参考)(※5)
あ 相当期間という概念
期間の定めのない使用貸借について
契約終了事由の1つとして『相当期間』という概念がある
『使用収益に足りる期間』のことである
※民法597条2項但書
い 補足事項
債務の履行・弁済に関するもの(前記※1)(前記※2)(前記※3)(前記※4)とは大きく異なる
単に(たまたま)同じような用語が使われているだけである
詳しくはこちら|一般的な使用貸借契約の終了事由(期限・目的・使用収益終了・相当期間・解約申入)
本記事では、督促・催告・相当期間に関する問題について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に期限までに履行(支払)がなされないケースに関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
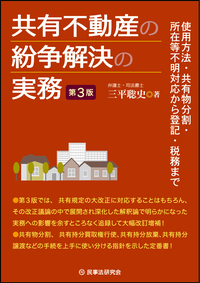
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!





