【取得時効の基本(10年と20年時効期間・占有継続の推定)】
1 土地の取得時効が生じる典型的状況
本記事では取得時効の基本的事項を説明します。
まず、現実に取得時効が適用される代表的なものを紹介します。
土地の取得時効が生じる典型的状況
結果的に越境してしまっていた
つまり、甲土地の所有者が乙土地の一部も占有していた
→越境部分について取得時効が完成した
このように土地の越境・曖昧な境界が背景にあることが多いです。
2 取得時効の条文規定
取得時効が成立する要件は、条文としてまとめて規定されています。
取得時効の条文規定
あ 要件
所有者以外が『他人の物』を占有していた
占有者は『所有の意思』をもっていた
平穏かつ公然と占有していた
占有が一定期間継続した(後記※1)
い 効果
占有者は所有権を取得する
※民法162条
条文上の規定はシンプルですが、いろいろな解釈論があります。
以下、説明を続けます。
3 『平穏』の意味(概要)
取得時効の要件の1つに占有が平穏である、というものがあります(前記)。
平穏とは、暴行・強迫によって占有したものではないというような意味です。
『平穏』の意味(概要)
4 2種類の取得時効期間
取得時効が完成する期間は2種類があります。
占有を開始した時点で、自分の所有物であると信じていて(誤信)、かつ、誤信したことに過失はないというケースでは10年間となります。
それ以外、つまり、自分の所有物であると知らなかった、または過失によって、自分の所有物であると誤信したという場合は20年間です。
2種類の取得時効期間(※1)
なお、取得時効の要件のうち大部分については占有による推定が適用されます(後記)。
しかし、10年の取得時効期間の要件である無過失で誤信したことは推定されません。
間違えやすいところなので注意が必要です。
また、(無)過失の判断基準や典型的な状況の判定については、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|10年の取得時効期間の要件である『無過失』の判断(判断基準と典型例)
5 所有の意思・自主占有の判断(概要)
前記のとおり、取得時効が成立するためには所有の意思が必要です。
自分の所有物として占有することを自主占有と呼びます。
自主占有の判断については、占有による推定が働きます(後記)。
そこで、主張・立証責任の配分は特殊ですし、また、実際の判断の枠組みについても多くの判例がルールを示しています。
自主占有の判断の枠組みについて別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|取得時効における自主占有(所有の意思)の主張・立証と判断基準
6 占有による推定と立証責任(概要)
取得時効の要件にはいくつかの事実があります(前記)。
これらの事実の大部分は、占有という事実によって推定されます。
要するに、取得時効を主張する者(占有者)が立証するハードルは大きく下げられているのです。
立証責任が時効取得を否定する側に転換(配分)されているともいえます。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|占有の態様と継続の推定(民法186条)(解釈整理ノート)
7 占有継続の推定(概要)
取得時効が成立するためには占有の継続が必要です(前記)。
実際の裁判で長期間の占有が継続したことを立証するハードルは高いです。
そこで、法律上、この立証は大きく緩和されています。
占有継続の推定(概要)
あ 立証時効の簡略化
『ア・イ』の2つの時点における占有を立証する
ア 占有開始時イ 時効完成時点
い 推定の効果
『あ』の2時点間の占有継続が推定される
※民法186条
詳しくはこちら|占有の態様と継続の推定(民法186条)(解釈整理ノート)
8 占有継続の推定と反証
占有継続の立証は緩和されています(前記)。
一方、この制度はあくまでも推定というものです。
否定する事実を立証することにより覆すことは可能です。
占有継続の推定と反証
あ 反対立証(基本)
占有継続を否定する立証があった場合
→占有継続の推定は覆る
い 反対立証の例
前記2時点の間で、占有が欠ける部分がある
本記事では、取得時効の基本的事項を説明しました。
実際には個別的な事情や立証のやり方次第で結果が大きく変わってきます。
実際に取得時効に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
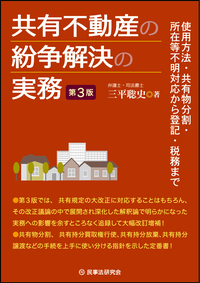
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!





