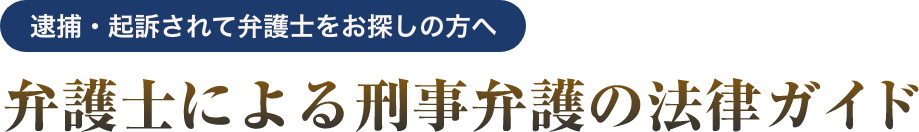【恐喝罪(刑法249条)の総合的解説(構成要件・判例・他罪との関係など)】
1 恐喝罪(刑法249条)の総合的解説(構成要件・判例・他罪との関係など)
本記事では、恐喝罪に関するいろいろな解釈や実務の実情など、全体像を説明します。
2 恐喝罪の特徴と発生件数
恐喝罪は、瑕疵ある意思に基づき被害者に財物を交付させ、ないしは財産上の利益を処分させる罪という意味で、詐欺罪とその構造が類似しています。異なるのは、手段が恐喝だという点です。しかし、刑事学的にみた罪質は、知能犯の代表とされる詐欺と全く異なり、粗暴犯の典型とされます。暴力団員さらに、少年の割合の多さも恐喝罪の特徴です。そして、恐喝罪は未遂犯の数が非常に多いという特徴があります。
法務省の犯罪白書によると、令和3年度に警察が認知した恐喝事件の件数は1,237件、うち検挙に至ったのは1,072件、検挙率は86.7%と高い数値を示しています。逮捕後の勾留請求率は97.8%であり、勾留請求が認容される確率は99%以上です。一方で、起訴率は30%以下と比較的低くなっています。
近年ではインターネット上での恐喝行為も増加しており、例えば令和元年には「半グレ集団」の幹部が「金返さんかい、殺すぞ」などと電話し現金を脅し取ろうとした恐喝未遂事件が報道されています。
3 刑法249条の条文
最初に刑法249条の条文を確認しておきます。条文はシンプルです。また、恐喝罪には未遂を罰する規定(刑法250条)があります。
刑法249条の条文
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
※刑法249条
4 恐喝罪の構成要件:客体客体→財物・財産上の利益
恐喝罪の客体は、他人の占有する財物と、財産上の利益です。恐喝罪においても、「損害」は要件として規定されてはいません。本条の客体としての財物には不動産も含まれます。
また、自己の所有する財物でも、他人の占有に属し、または公務所の命により他人が看守する場合には他人の財物とみなされます。電気も財物とみなされます(刑法251条)。
5 恐喝罪の構成要件:恐喝行為
(1)基本→犯行側圧に至らない脅迫
恐喝罪は、交付(処分)に向けられた恐喝行為により被害者が畏怖し、その処分行為により財物・財産上の利益が移転することにより完成します。
恐喝とは、相手の反抗を抑圧しない程度の脅迫で、財物・財産上の利益を得るために用いられるものをいいます(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。どの程度の脅迫が恐喝罪を構成するかは、具体的な行為事情を踏まえて実質的に判断されます。
たとえば、暴力団関係者によるみかじめ料要求行為は恐喝罪の実行行為に当たります(東京地判平成14年11月19日判時1807号158頁)。たとえば、暴行が繰り返される可能性を示すことにより、相手を畏怖させ得ます(最決昭和33年3月6日刑集12巻3号452頁)。
(2)強盗罪との判別
脅迫が犯行を抑圧する程度に達した場合は強盗罪に分類されることになります。判例は主に暴行・脅迫の程度が、相手の反抗を抑圧するに足りるかどうかという外形的基準で区別しています。教科書事例としては、拳銃や刃物をつきつける行為などは反抗を抑圧するとして強盗罪、口頭で「殺すぞ」と言うような脅迫は恐喝罪に該当するという方向性です。ただし、実際には反抗を抑圧しない程度か否か、つまり恐喝と強盗の判別がはっきりしない事例も多いです。
(3)害悪の対象→制限なし
脅迫罪(刑法222条)の脅迫とは異なり、相手またはその親族の生命・身体・名誉・自由・財産に関する害悪の告知に限定されません。相手の婚約者に対する害悪も含まれます。
(4)害悪の内容の適法性→適法も含む
また、害悪の内容そのものが、犯罪を構成するものである必要はありません。相手の犯した犯罪事実を捜査機関に申告する旨告げる行為も、それにより口止め料を得れば本条に該当します(最判昭和29年4月6日刑集8巻4号407頁)。
(5)脅迫の対象→処分に向けられたもの
恐喝罪の手段としての脅迫は、詐欺罪の欺罔行為同様、処分に向けられたものでなければなりません。脅して注意をそらし、その間に占有を奪った場合は窃盗罪であり、恐喝罪の実行の着手は認められません。被害者の畏怖と未遂脅迫により畏怖状態に陥り、その結果処分したという関係が必要です。脅迫したが被害者は全く畏怖せず、例えば憐憫の情から交付した場合は、恐喝未遂となります。
6 交付行為
(1)恐喝罪の交付
詐欺罪と同様に、被害者側の財産的交付(処分)行為が必要です。ただ、恐喝罪においては、被害者が自ら交付・処分する場合のみならず、畏怖して黙認しているのに乗じて奪取する場合も、処分行為は認められます(最判昭和24年1月11日刑集3巻1号1頁)。
(2)黙示の処分
最決昭和43年12月11日(刑集22巻13号1469頁)は、飲食代金の請求を断念させようと、脅迫的言辞を弄し、飲食店主を畏怖させて支払いを免れた事案に関し、被害者側の黙示的な少なくとも支払い猶予の処分行為が存在し2項恐喝罪が成立するとしました。昭和30年代の詐欺罪判例が、被害者が単に督促をしないというだけでは債務を一時免れたとしても処分行為とはいえないとしていたことと比較し、処分概念は緩やかです。処分行為概念は、詐欺罪と恐喝罪で同一ではありません。
ただ、このような不作為・黙示の処分行為を広く認めると、意思に反して奪取する強盗罪との限界が微妙となります。理念的には、「意思に反して奪う強盗と、瑕疵ある意思に従って奪う恐喝」という形で区別されますが、主として外形的な暴行・脅迫の程度が反抗を抑圧する程度に強いか否かによっています。
(3)交付行為に関する諸問題
脅迫が向けられる被恐喝者と被害者は、詐欺罪同様、同一人である必要はありません。ただ両者が別人であるときは、被恐喝者は被害者の財物・財産上の利益を処分し得る権限または地位を有することが必要です(大判大正6年4月12日刑録23巻339頁)。松山地判平成22年12月1日(裁判所Web)は、被害者に代わりその父親が金銭を出捐した場合について、恐喝行為と金銭交付との間の因果関係を認めました。
恐喝罪の未遂には、障害未遂と中止未遂の2種類があります。
障害未遂とは、被害者が抵抗した・警察に通報されたといった理由で犯行を遂げられなかった場合を指し、裁判官の判断次第で刑は減軽されます(刑法43条本文)。
これに対して、中止未遂とは、犯行を自ら思いとどまることであり、この場合には必ず刑が減軽・免除されます(同条但書)。
脅迫して金員を指定の預金口座に振込送金させたが、捜査官の指示により預金払戻しができない体制の整った状況にあった場合には、1項恐喝の未遂に過ぎないとされています(浦和地判平成4年4月24日判時1437号151頁)。現金の交付を直接に受けたと実質的に同視することはできないし、そのような段階では、財産上の利益を得たことにもなりません。
事情を知って喝取金の交付を受ける行為は、恐喝罪の実行行為であり、(共同)正犯を構成するかにみえます。しかし、大阪高判平成8年9月17日(判タ940号272頁)は、YがAから金を脅し取ろうとしていることを知りながら、Yの依頼により、AをYらに引き合わせYが脅迫を加えた後Yに代わって喝取金を受け取ったXにつき、恐喝の共同正犯ではなく幇助としました。喝取金の帰属などの事情を勘案し、「自己の犯罪」とみることができなければ、実行行為の一部を行っても幇助となります。
7 罪数・他罪との関係
(1)罪数
1個の恐喝行為で同一人から数回にわたって金員の交付を受けた場合には1個の恐喝罪が成立し、単一の犯意に基づく複数回の脅迫により財物を交付させた場合には、1個の恐喝罪が成立します。1個の恐喝行為で同一人から財物と財産上の利益を得た場合には、包括して1個の恐喝罪が成立します(大判明治45年4月15日刑録18巻469頁)。1個の恐喝行為で財物交付の約束をさせた後に、その財物を交付させた場合にも、1個の1項恐喝罪が成立します。
1個の恐喝行為により数人から金品の交付を受ける場合には、数個の恐喝罪が成立し、観念的競合となります。本罪の手段として用いられた暴行により傷害の結果が生じた場合には、恐喝罪と傷害罪との観念的競合となります。
暴行により被害者が畏怖しているのに乗じ、引き続き接着した場所で財物を喝取したときは、恐喝の犯意が暴行後に生じたとしても、全体として評価して恐喝罪一罪が成立します(東京高判平成7年11月27日東高刑時報46巻1=12号90頁)。ここでも、恐喝を認めるには、犯意発生後に新たな脅迫行為が必要ですが、強取の場合以上に、畏怖状態が既に存在する以上軽微な態様でも恐喝と認定されるでしょう。暴行により傷害が生じた場合も、両者は包括一罪となります。
東京地判平成8年4月16日(判時1601号157頁)は、XとYは意思を通じAに暴行を加えたところ、後から現場に到着したZが、Aの畏怖状態を利用して金員を喝取しようと企て金員の交付を要求したところ、X、YもZの意図を察し暗黙のうちに意思を通じた上で、ZがAに暴行を加えて畏怖させてBに現金を届けさせて喝取した事案につき、いずれの暴行によりAが傷害を負ったか不明だったが、恐喝と傷害は被害者が同一で時間的・場所的に近接しており、事前の暴行が実質的に恐喝の手段となっている関係も認められるから混合的包括一罪であるとし、全暴行に因果性を有するXYはもとより、途中から関与したZも犯行全体について共同正犯としての罪責を負うとしました。
(2)強盗罪との関係
同一人に対して恐喝に引き続いて強盗傷害罪を犯した場合には、包括して重い刑法240条一罪が成立します(東京高判昭和34年8月27日高刑集12巻7号707頁)。相手方の反抗を抑庄するに足りる程度の脅迫が加えられたが、被害者が反抗抑圧に至らない程度の恐怖心を生じた結果、財物の持ち去りを黙認した場合には強盗未遂罪が成立し、恐喝既遂罪との観念的競合となります(大阪地判平成4年9月22日判タ828号281頁)。
(3)詐欺罪との関係
財物を交付させる際に欺罔(だます行為)と恐喝の両手段が用いられた場合、両手段が併用され、錯誤と畏怖とが原因となって財物が交付された場合には、詐欺罪と恐喝罪が成立し観念的競合となります。
これに対し、脅迫の中に虚偽の部分があっても、被害者の決意が畏怖に基づく場合には恐喝罪のみが成立して詐欺罪には該当しません。例えば、祈禱を受けないと命が危ないと脅し金員を交付させる行為は、恐喝罪のみが成立します(広島高判昭和29年8月9日高刑集7巻7号1149頁)。
警察官を装った者が窃盗犯人に対し、「警察の者だが取調の必要があるから差し出せ」と虚偽の事実を申し向けて盗品を交付させた場合も、警察官と称する虚偽が含まれていてもそれが畏怖させる一材料であり、畏怖の結果、財物を交付するに至った場合は、恐喝罪となります(最判昭和24年2月8日高刑集3巻2号83頁)。
遺産相続に関し虚偽の事実を申し向けて、身体・財産に危害を加えられることになるかもしれないと畏怖させ、5,000万円を交付させた事案に関し、話の内容は虚偽ではあっても畏怖させるに足りる害悪の告知であり、被害者が畏怖していることを認識した上で現金を受領したのであるから恐喝罪が成立するとされました(東京地八王子支判平成10年4月24日判タ995号282頁)。
(4)その他の罪との関係
恐喝の目的で監禁した場合、監禁罪と恐喝罪とは併合罪です(最判平成17年4月14日刑集59巻3号283頁)。人を略取・誘拐した者が、身の代金を要求して財物を得た場合、本罪は身の代金目的略取罪(225条の2②前段)に吸収されます。恐喝の目的で業務を妨害するような虚偽事項を新聞に掲載して畏怖させ、金員を交付させた場合には、業務妨害罪と恐喝罪が成立し、牽連犯となります(大判大正2年11月5日刑録19巻1114頁)。
盗品であることを知りながらこれを所持する者を恐喝して盗品の交付を受けた場合には、盗品譲受け罪と恐喝罪とは観念的競合となります(大判昭和6年3月18日刑集10巻109頁)。恐喝行為により賄賂を収受した場合には、収賄罪と恐喝罪の観念的競合となります。
8 権利行使と恐喝罪(概要)
一般的に権利行使の場面で相手方がプレッシャーを感じることはあります。そこで、適法な権利行使と恐喝罪の境界線が問題となります。これについては、ユーザーユニオン事件をはじめ、多くの実例(判例)があります。別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|権利行使と脅迫罪・恐喝罪の区別・判断基準(正当な行為と犯罪の境界線)
詳しくはこちら|ユーザーユニオン事件の事例分析(権利行使と恐喝罪の境界線)
9 実務上の重要ポイント
令和3年の統計データによれば、恐喝罪の検挙率は86.7%と高く、逮捕後の勾留率も極めて高いことから、一旦恐喝罪で逮捕されると長期間の身体拘束を受ける可能性が高いといえます。一方で起訴率は30%以下と比較的低く、被害者との示談が成立すれば不起訴になる可能性が高まります。弁護戦略としては、早期に被害者との示談交渉を進めることが有効です。
また、令和7年(2025年)6月1日からは、懲役刑・禁錮刑が「拘禁刑」に統合される予定であり、恐喝罪の法定刑も10年以下の拘禁刑となります。この法改正による実質的な量刑への影響は少ないと考えられますが、弁護実務上は注視すべき点です。
近年ではインターネット上での脅迫・恐喝事案も増加しており、SNSやメールを通じた恐喝行為についても、従来の恐喝罪の枠組みで対応されています。これらの証拠は電子的に保存されることが多いため、事案によっては証拠隠滅のリスクが低く、在宅での捜査協力が認められる可能性もあります。
10 関連テーマ
(1)脅迫罪・恐喝罪・強要罪の基本的事項と違い
11 参考情報
参考情報
本記事では、恐喝罪の全体像について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に恐喝罪に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。