【不動産競売で不動産が損傷・滅失した場合の救済手段(売却不許可・売却許可取消)】
1 不動産競売で不動産が損傷・滅失した場合の救済手段(売却不許可・売却許可取消)
競売の不動産(主に建物)に損傷が発覚した、または不動産が滅失した場合、そのまま手続を進めることは支障があります。そこで、手続上の救済手段が用意されています。
本記事では、不動産の損傷や滅失の場合の売却不許可や売却許可取消について説明します。
2 不動産の損傷・滅失の場合の手続内の救済手段のまとめ
不動産の損傷のケースと滅失のケースで救済手段は違いますし、特に損傷ケースでは、損傷したタイミングと発覚したタイミングによって救済手段の内容が違ってきます。
最初に全体のまとめを挙げておきます。それぞれの内容については、以下説明します。
<不動産の損傷・滅失の場合の手続内の救済手段のまとめ>
あ 損傷
ア 損傷時期=買受申出前(見落としていたケース)(ア)発覚時期=売却許可決定確定前
60条2号=売却実施やり直し・71条1号=売却不許可
(イ)発覚時期=売却許可決定確定後
75条類推=売却許可取消
イ 損傷時期=買受申出後〜代金納付前(見落としではないケース)
75条=売却不許可・売却許可取消
ウ 損傷時期=代金納付後
救済なし
い 滅失
ア 滅失時期=代金納付前
53条=手続取消
イ 滅失時期=代金納付後
救済なし
3 競売物件売却の流れ(前提)
救済手段の内容は、損傷などが生じたタイミングや発覚したタイミングによって違います。理解しやすくなるように、最初に、競売手続の流れを確認しておきます。
競売手続の流れ(前提)
↓
売却基準価額の決定
↓
買受申出(入札)
↓
開札
↓
売却許可決定
↓
売却許可決定の確定
↓
代金納付=所有権移転
4 買受申出(入札)前の損傷(見落としていたケース)
最初に、買受申出、つまり入札の前に損傷が存在していたケースについて説明します。要するに、最初からあった損傷を気づかないまま不動産の評価や入札といった手続が進んで、後から損傷が発覚した、というケースです。
(1)売却基準価額変更と売却不許可
このように、最初からあった損傷が、後から発覚した場合のルールとして、売却基準価額の変更があります。売却基準価額とは、入札金額の基準を定めるものです。要するに、入札開始より前に損傷が発覚したら、売却基準価額に損傷によるマイナス評価を反映させてから入札を行う、ということです。
損傷が発覚した時にはすでに入札が終わっていた場合には、次のステップである売却許可の判断の中で裁判所が不許可とする、つまり入札をキャンセルすることになります。
裁判所が損傷に気づいて売却不許可にしてくれるとは限らないので、通常、入札者(最高価買受申出人)から裁判所に不許可の申出をして、不許可にするよう要請することになります。
売却基準価額変更と売却不許可
あ 売却基準価額の変更
執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。
※民事執行法60条2項
い 売却不許可
第七十一条 執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
・・・
七 売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
・・・
※民事執行法71条7号
(2)買受申出前の損傷への75条類推適用→肯定方向
では、最初から存在した損傷が発覚した時にはすでに売却許可決定が出て、さらにそれが確定してしまっていた、というケースではどうでしょうか。確定した売却許可決定を解消するには、売却許可の取消申立を使います。ただこの売却許可取消申立は、民事執行法75条1項の条文上、買受申出(入札)後に生じた損傷だけが対象になっています。では、最初から(買受申出前に)存在した損傷のケースでは取消申立はできないかというとそうではありません。民事執行法75条の類推適用を認める見解が一般的です。つまり、最初から損傷が存在したケースでも売却許可取消申立はできる、ということになります。
なお、これとは別に執行抗告もできる、という見解もあります。
買受申出前の損傷への75条類推適用→肯定方向
あ 解釈→類推適用肯定方向
本条(注・民事執行法75条)は買受けの申出前の損傷を直接規律するものではないから、それが買受けの申出後に判明した場合においては類推適用の可否が問題となるところ、通説は、所定の要件・・・の下で、積極説をとっている。
い 実際に使う場面→売却許可確定後のみ
ただし、損傷が売却許可決定の確定前に判明したときは、上記の通り別に売却不許可事由(71(7))を主張する方法があるため(70・74②)、本条の類推適用がとくに意味をもつのは、売却許可決定の確定後に判明したときである(鈴木=三ヶ月・注解(3)121頁〔園尾〕参照)。
※水元宏典稿/伊藤眞ほか編『条解 民事執行法 第2版』弘文堂2022年p795
(3)代金納付後の救済手段→なし
では、損傷が発覚した時には、すでに最終段階である代金納付が終わっていた場合はどうでしょうか。この場合は競売手続の中では救済手段はありません。
ただし、実体法(民法)上の救済手段は別です。
詳しくはこちら|競売における担保責任(権利・種類・品質の不適合)
5 買受申出(入札)後の損傷(見落としではないケース)
(1)民事執行法75条→売却不許可・売却許可取消
次に、損傷が生じたのが、買受申出(入札)の後であったケースについて説明します。つまり、競売手続の最初の段階の物件の調査で見落としがあったわけではなく、その後で損傷が生じた、というケースです。
このケースについては、民事執行法75条1項が救済手段を用意しています。
売却不許可決定が出る前であれば、売却不許可の申出をする、という手段です。
売却許可決定が出てしまった後であれば、すでに出てしまった売却許可決定の取消を申し立てる、という手段です。
民事執行法75条→売却不許可・売却許可取消
第七十五条 最高価買受申出人又は買受人は、買受けの申出をした後天災その他自己の責めに帰することができない事由により不動産が損傷した場合には、執行裁判所に対し、売却許可決定前にあつては売却の不許可の申出をし、売却許可決定後にあつては代金を納付する時までにその決定の取消しの申立てをすることができる。ただし、不動産の損傷が軽微であるときは、この限りでない。
※民事執行法75条1項
(2)損傷発生が代金納付後→適用なし
民事執行法75条には、売却許可取消の申立ができるタイミングは代金納付の時までである、と書いてあります。
損傷発生が代金納付後→適用なし
※水元宏典稿/伊藤眞ほか編『条解 民事執行法 第2版』弘文堂2022年p797
代金納付の後に損傷が発生した場合は、売却許可取消はできないのですが、民法上の担保責任は引渡時までに損傷が発生した場合にも適用される(危険負担は買主に移転していない)見解が優勢です(後述)。
(3)損傷発覚が代金納付後→適用なし方向
買受申出後、かつ、代金納付前に損傷が生じたけれど、発覚した時はすでに代金納付後だった、というケースはどうでしょうか。
ここで、競売手続内で買受人を救済するとしたら競売手続(全体)の取消しかありません。条文上、競売手続の取消が認められるのは滅失などです。損傷も滅失と同じように扱って競売手続取消を認める見解もありますが一般的には否定されています。
損傷発覚が代金納付後→適用なし方向
あ 一般的見解→適用なし
ア 条解民事執行法
また、代金納付前の損傷が代金納付後に判明した場合においても、本条(注・民事執行法75条)は適用されないと解するのが一般的である。
代金納付後の段階で売却許可決定の取消しを認めることは、手続の安定を大きく損なうからである。
※水元宏典稿/伊藤眞ほか編『条解 民事執行法 第2版』弘文堂2022年p798
イ 注釈民事執行法
・・・買受人が代金を納付した後に不動産が損傷したときは、滅失の場合と同様に、買受人が危険を負担することになる。
代金納付前に既に損傷していた場合でも、買受人が本条一項の申立てをしないで代金を納付したときは、同様である。
単に不動産が損傷しただけでは、強制競売手続の取消事由とならないからである(後記三2の末尾)。
※近藤崇晴稿/香川保一ほか監『注釈民事執行法 第4巻』金融財政事情研究会1983年p94
い 例外
ア 認める余地あり
ただし、例外を認める余地もある。
※水元宏典稿/伊藤眞ほか編『条解 民事執行法 第2版』弘文堂2022年p797、798
イ 例外の内容→53条類推適用
代金納付後であっても配当等の実施前であれば、手続の巻き戻しが原理的にできないわけではないから、買受人が実体法に従い売買契約(競売)を解除する場合には、解除によって不動産の移転が遡及的に妨げられるとの理解を前提に、53条の類推適用を認める考え方も成り立つ(中野519頁注(16)参照。同旨、中野=下村548頁注(18))。
※水元宏典稿/伊藤眞ほか編『条解 民事執行法 第2版』弘文堂2022年p798
ウ 民事執行法53条の条文
(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
第五十三条 不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなつたときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。
※民事執行法53条
なお、否定されるのはあくまでも競売手続内での救済だけです。民法上の担保責任は提要されます(後述)。
6 売却不許可・売却許可取消となる損傷の「軽微」の基準
以上のように、損傷のケースでは、売却不許可とする、またはすでに出された売却許可決定を取り消すルール(民事執行法75条)があります。ただし、民事執行法75条1項には損傷が軽微である場合が除外されています。つまり損傷が軽微である場合は救済されないのです。
この軽微がどの程度か、ということが問題となることがよくあります。抽象的ですが、基準としては売却基準価額を変更すべき程度といえるかどうか、ということになります。
売却不許可・売却許可取消となる損傷の「軽微」の基準
かかる基準において軽微なものであれば、たとえ損傷があったとしても、手続の安定が重視されるべきだからである。
※水元宏典稿/伊藤眞ほか編『条解 民事執行法 第2版』弘文堂2022年p798
7 価値的損傷(予期せぬ物件)→売却不許可・売却許可取消
(1)価値的損傷(予期せぬ物件)への75条類推→肯定
前述のように民事執行法75条は、「損傷」があった場合に適用(救済)するルールです。ところで実際の競売では、損傷以外にも、予期せぬ不具合が発覚することがとても多いです。いろいろな不具合で不動産の価値が下がっているという場合にも、価値の損傷と考えて、「損傷」として扱う、つまり売却不許可や売却許可取消を認める傾向があります。
価値的損傷(予期せぬ物件)への75条類推→肯定
(本条は、相当程度拡張して類推適用され、予期せぬ物件を購入した買受人救済の機能を果たしているという(執行実務・不動産執行(下)151頁))。
※水元宏典稿/伊藤眞ほか編『条解 民事執行法 第2版』弘文堂2022年p799
(2)売却不許可・売却許可取消の対象となる予期せぬ物件の例
価値的損傷として、売却不許可や売却許可取消を認める不具合、不都合にはいろいろなものがあります。面積不足や法令上の制限、追加費用がかかること、暴力団の占有、占有権原(敷地権など)がないことが発覚したようなケースが挙げられます。
さらに、自殺や殺人、事故死などのいわゆる心理的瑕疵が発覚したケースも価値的損傷として扱うことがあります。
詳しくはこちら|不動産競売における心理的瑕疵の救済(売却不許可・売却許可取消)
売却不許可・売却許可取消の対象となる予期せぬ物件の例
①実測面積の不足事案、
②法令上の制限事案、
③追加費用の発生事案、
④第三者または暴力団の占有事案、
⑤敷地権の欠缺事案、
⑥シロアリ等の被害事案、
⑦自殺・殺人・事故死等の現場事案
などがありうる。
※水元宏典稿/伊藤眞ほか編『条解 民事執行法 第2版』弘文堂2022年p799
8 滅失したケース
(1)民事執行法53条→競売手続取消
次に滅失のケースの救済手段を説明します。たとえば建物の競売で、大震災が生じて建物が全壊したようなケースです。
不動産が滅失した、つまり完全に存在しなくなったので、もう、競売手続全体を解消することになります。競売手続の取消です。
損傷のように複雑なルールはありません。
民事執行法53条→競売手続取消
第五十三条 不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなつたときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。
※民事執行法53条
(2)代金納付後に滅失→救済なし
前述のルールは代金納付前に滅失したことが当然の前提となっています。
逆に、代金納付後に滅失した場合は、すでに危険負担は新所有者(買受人)に移転していますので、理論的に救済されません。
9 関連テーマ
(1)民法上の担保責任
以上で説明したのは、不動産に損傷や滅失などが生じた場合の競売手続内での救済手段です。これとは別の救済手段として民法上の担保責任もあります。担保責任に関しては、手続内での救済手段とは、カバーする範囲が異なります。具体的には、不動産の引渡時までに損傷や滅失が発生した場合に解除や代金減額請求(つまり代金の全額や一部の返還請求)が認められます。
詳しくはこちら|競売における担保責任(権利・種類・品質の不適合)
本記事では、不動産競売で不動産が損傷、滅失した場合の救済手段について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に不動産の競売に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
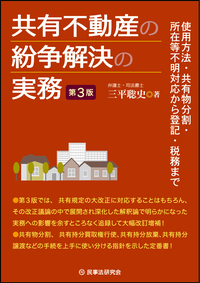
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!





