【質権の基礎と実務での活用ガイド(特徴・企業間取引の実例・手続)】
1 質権の基礎と実務での活用ガイド(特徴・企業間取引の実例・手続)
質権はややマイナーな担保物権です。ただ、特徴をしっかりと理解すれば、状況によってはメリットを活かした使い方ができます。
本記事では、質権について基礎的な知識から実務での活用方法について説明します。
2 質権に関する基礎知識
質権(しちけん)とは、債権者が債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、債務が弁済されない場合にその物から優先的に弁済を受けることができる担保物権です。民法342条に規定されており、当事者間の合意によって成立する約定担保物権に分類されます。
質権は、その目的物の種類によって、主に「動産質」「不動産質」「権利質」の3種類に分けられます。動産質とは、不動産以外の有体物に対して設定される質権であり、質屋営業が典型例です。不動産質とは、土地や建物などの不動産に設定される質権で、債権者がその不動産を使用収益することができます。権利質とは、債権や株式、知的財産権などの財産権に対して設定される質権で、売掛金債権や火災保険金請求権などが対象となります。
3 質権の特徴と効力
質権の最も重要な特徴は、債権者に目的物の占有が移転することです。この占有の移転により、質権は二つの主要な効力を持ちます。一つは留置的効力で、債権者が債務弁済まで目的物を占有し続けることで、債務者に心理的圧力をかけ、間接的に弁済を促す効果があります。もう一つは優先弁済的効力で、債務不履行の場合に、質権者は他の一般債権者に先立って質物から優先的に弁済を受けることができます。
質権には、他の担保物権と同様に以下の性質があります。付従性とは、質権がその担保する債権が存在しなければ成立せず、債権が消滅すれば質権も消滅する性質です。随伴性とは、質権がその担保する債権と運命を共にし、債権が譲渡されれば質権も共に移転する性質です。不可分性とは、債務の一部が弁済されても、残債務が完済されるまでは質物全体について質権の効力が及ぶ性質です。物上代位性とは、質物が滅失や毀損した場合に、その代わりに債務者が受け取るべき金銭(例えば、火災保険金)などに対しても質権の効力が及ぶ性質です。
4 質権の種類と設定方法
質権の設定方法は、その種類によって異なります。
(1)動産質
動産質は、不動産以外の有体物(例:貴金属、美術品など)に対して設定される質権です。
設定には質権設定契約の締結と目的物の引渡しが必要です。
第三者に対抗するためには、質権者が継続して動産を占有していることが必要です。
ただし、麻薬やわいせつ文書などの禁制品、譲渡できない物、登記された船舶、自動車、航空機などは動産質の目的とすることができません。
(2)不動産質
不動産質は、土地や建物に対して設定される質権です。設定には不動産の引渡しが効力要件であり、第三者に対抗するためには登記が必要です。不動産質権の存続期間は10年以内とされており、それより長い期間を定めた場合でも10年に短縮されます。期間満了時には10年以内の期間で更新が可能です。
(3)権利質
権利質は、債権や株式、知的財産権などの財産権に設定される質権です。
設定要件は権利の種類によって異なります。金銭債権の場合は、第三債務者への通知またはその承諾が必要です。第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です。
株式の場合、株券発行会社では株券の占有継続による略式質と株主名簿記載による登録質があります。
保険金請求権の場合は保険会社への通知が必要です。
特許権などの知的財産権では、登録原簿への質権設定登録が必要です。
質権設定契約書には、被担保債権(質権によって担保される債権)と質権の目的物を明確に特定することが重要です。被担保債権の範囲(元本、利息、違約金など)や担保の対象となる物や権利の詳細を記載します。
5 質権と抵当権の比較
質権と抵当権は、いずれも債権を担保するための権利ですが、最も大きな違いは目的物の占有の有無にあります。質権では債権者に目的物の占有が移転するのに対し、抵当権では債務者が目的物の占有を保持し、使用収益を続けることができます。
この違いから、実務上の選択基準として、不動産を担保とする場合は一般的に抵当権が選ばれます。抵当権であれば、債務者は担保となる不動産を使用し続けることができるため、事業や生活への影響が少ないからです。一方、動産や債権を担保とする場合は、質権が適切な場合があります。特に、債権質は債権者が直接取り立てることができるため、迅速な債権回収が期待できます。
また、抵当権は主に不動産、地上権、永小作権に対して設定されるのに対し、質権は動産、不動産、そして権利(債権、株式など)に対しても設定可能です。ただし、現代においては、不動産質権は抵当権に比べて利用されることが少なくなっています。
6 企業間取引における質権活用事例
企業間取引において、質権は債権回収の確実性を高めるために活用されています。
(1)B2B取引での売掛金債権への質権設定
企業間の取引では、商品やサービスを提供した後に代金が支払われる信用取引が一般的です。この未回収の売掛金債権は質権の設定に適した担保となり得ます。例えば、継続的な取引によって安定した売掛金債権が発生している場合、債権者はこの売掛金債権に質権を設定することで、債務不履行のリスクを低減できます。債権質は、債権者と債務者の合意により成立し、質権者は第三債務者(売掛金の支払義務者)から直接取立てることができます。
(2)中小企業の資金調達における活用方法
中小企業は、不動産などの担保に乏しい場合でも、保有する売掛金債権や在庫を担保に資金調達を行うことができます。
政府系の金融機関や信用保証協会も、流動資産担保融資保証制度などを通じて、中小企業の売掛金債権を活用した資金調達を支援しています。例えば、原材料の仕入れ資金や運転資金の確保のために、売掛金債権に質権を設定する事例があります。また、事業承継や事業再生の局面においても、質権が活用されることがあります。
(3)保険金請求権への質権設定
住宅ローンにおける火災保険金請求権への質権設定は、質権の典型的な活用例です。
金融機関が住宅ローンを貸し付ける際、担保として火災保険金請求権に質権を設定することがあります。これにより、万が一火災が発生した場合、金融機関は保険金から優先的に債権の弁済を受けることができます。この場合、契約者・被保険者・質権者の記名・捺印のある質権設定承認請求書の提出が必要となります。また、住宅ローンを完済した際には、質権を抹消する手続きが必要です。
7 質権設定・実行の手続きと費用
質権の設定手続きと実行方法、およびそれにかかる費用は以下の通りです。
(1)質権設定手続きの流れ
質権設定の手続きは質権の種類によって異なります。
特許権を対象とする権利質の場合、質権設定契約を締結し、特許庁に登録申請を行う必要があります。
火災保険の保険金請求権を対象とする権利質の場合、金融機関との間で質権設定契約を結び、保険会社に通知する手続きが必要です。
いずれの場合も、質権設定契約書に被担保債権と質権の目的物を明確に特定する必要があります。
(2)登記費用や専門家報酬の目安
動産質の場合、動産譲渡登記の登録免許税は特別措置により1件あたり7,500円です。
不動産質の場合、登録免許税は債権金額の1000分の4です。
権利質の場合、債権譲渡登記または質権設定登記の登録免許税は、債権の個数が5,000個以下の場合は1件につき7,500円、5,000個を超える場合は1件につき15,000円です。
司法書士への報酬は事務所によって異なります。
質権設定契約書自体には、原則として印紙税は課税されません。ただし、債権譲渡担保契約書など関連する契約書には印紙税が課税される場合があります。
(3)債務不履行時の質権実行手続き
債務者が債務を履行しない場合、質権者は質権を実行して未払いの債権を回収することができます。
動産質の場合、原則として民事執行法に基づき動産競売によって実行され、動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に申し立てます。ただし、正当な理由がある場合には、裁判所の許可を得て、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることも認められています。
不動産質の場合、民事執行法に基づき担保不動産競売によって実行する必要があり、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
権利質の場合、金銭債権を目的とする質権者は第三債務者に対して直接その債権の取立てを行うことができます。
株式を目的とする質権の場合、競売などの法的手続きを通じて株式を売却し、債権の回収を図ります。
8 実務上の注意点と最新動向
質権を実務で活用する際の注意点と最新の法的動向について解説します。
(1)実務上の留意点と専門家の見解
実務上、債権質権設定契約においては、担保される債権(被担保債権)と質権の対象となる債権を明確に特定することが非常に重要です。また、第三債務者に対する対抗要件を備えるために、確定日付のある通知または承諾を得るか、債権譲渡登記を行う必要があります。
金融機関は、融資審査において質権の対象となる財産の価値や換金性を慎重に評価します。不動産を担保とする場合、固定資産税評価額や市場価格、建物の耐用年数などが考慮されます。売掛金債権を担保とする場合は、債務者の信用力や取引状況、売掛先の信用力などが評価されます。
譲渡禁止特約が付された債権を質権の目的とする場合には、特約の存在について善意の場合のみ質権設定が有効となります。ただし、銀行預金債権などについては、譲渡禁止特約が一般的に知られているとして、善意の主張が認められない場合があります。
(2)民法改正が質権実務に与えた影響
平成29年の民法改正では、債権譲渡に関する規定が大きく見直され、権利質にも影響を与えました。例えば、将来債権を質権の目的とできることが明記されました。また、債務者が譲渡制限の意思表示について悪意または重過失である譲受人(質権者を含む)に対しては、債務の履行を拒むことができるようになりました。さらに、更改後の債務への担保の移転に関する規定も改正され、質権についても適用されることになりました。
(3)今後予想される法改正の方向性
現在、法務省の法制審議会では、担保法制の見直しが進められており、譲渡担保の明文化や、事業全体を担保とする新たな担保権(企業価値担保権)の創設などが検討されています。これらの法改正が実現すれば、質権を含む担保権の実務に大きな影響を与える可能性があります。特に、企業価値担保権は、従来の個別資産担保とは異なる包括的な担保の仕組みであり、今後の動向が注目されています。
9 Q&A(よくある質問)
質権に関して、よく寄せられる質問とその回答をご紹介します。
(1)質権と抵当権はどちらが有利か
どちらが有利かは、担保の目的物や取引の状況によって異なります。
不動産を担保とする場合は、一般的に抵当権の方が有利です。抵当権を設定しても、債務者は不動産の使用収益を継続できるため、事業や生活への影響が少ないからです。
一方、動産や債権を担保とする場合は、質権が適切な場合があります。特に、債権質は債権者が直接取り立てることができるため、迅速な債権回収が期待できます。有価証券などの担保には、質権が利用されることが多いです。
(2)質権設定・抹消手続きについて
質権設定の手続きは質権の種類によって異なります。
特許権を対象とする権利質の場合、質権設定契約を締結し、特許庁に登録申請を行う必要があります。
火災保険の保険金請求権を対象とする権利質の場合、金融機関との間で質権設定契約を結び、保険会社に通知する手続きが必要です。
質権抹消の手続きは、担保となっている債務が完済された後に行われます。
火災保険の質権の場合、金融機関から質権消滅承認請求書が発行され、保険会社に提出することで抹消手続きが行われます。抵当権と同様に、質権の抹消登記も必要となる場合があります。
(3)質権と先取特権の違い
質権は当事者間の契約によって成立する約定担保物権であるのに対し、先取特権は法律の規定により当然に成立する法定担保物権です。先取特権は、例えば、不動産の工事による請負代金債権などについて、法律上当然に発生する担保物権で、債権者と債務者との間の契約によって成立するものではありません。一方、質権は債権者と債務者(または第三者)との間の契約によって成立します。また、先取特権者は目的物を占有する権利はなく、質権のような留置的効力はありません。
先取特権については、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|先取特権の基本(種類・優先順位・実行=競売申立方法・活用例)
10 関連テーマ
(1)質権の総則規定(民法342条〜351条)
民法上の質権に関して共通する条文とその解釈については別の記事に整理しています。
詳しくはこちら|質権の総則規定(民法342条〜351条)(解釈整理ノート)
本記事では、質権の基礎と実務での活用について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に質権などの担保の活用や債権回収に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
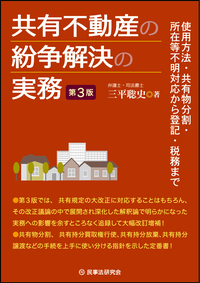
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!





