【占有の態様と継続の推定(民法186条)(解釈整理ノート)】
1 占有の態様と継続の推定(民法186条)(解釈整理ノート)
民法186条は、占有の態様と占有の継続を推定する、という規定です。実務では、このルールだけを使うわけではなく、取得時効など、別の規定を使う場面で前提として使います。本記事では、民法186条についてのいろいろな解釈を整理しました。
2 民法186条の条文
(1)民法186条の条文
民法186条の条文
第一八六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
※民法186条
(2)民法186条の趣旨
民法186条の趣旨
占有制度は物の支配の秩序を維持することを目的としており、社会に現に存する占有は瑕疵をおびない正当なものであるといちおう推定することが、その制度の目的に適する
3 占有の態様に関する推定(1項)
占有の態様に関する推定(1項)
あ 所有の意思をもって占有
自主占有(所有の意思がある占有)であることが推定される
い 善意の占有
善意(無権利であることを知らない状態)であることが推定される
う 平穏な占有
平穏な占有であることが推定される
「平穏な占有」とは、暴行または強迫によらない占有を意味する
他人から占有が不法であるという抗議を受けたという事実があっても、それだけでは占有が平穏でないことにはならない
※大判大正5年11月28日民録22輯2320頁
え 公然の占有
公然の占有(隠秘によらない占有)であることが推定される
4 占有の継続に関する推定(2項)
占有の継続に関する推定(2項)
あ 規範
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有はその間継続したものと推定する
この規定によって、時効取得を主張する者の挙証責任は著しく軽減される
い 具体例
例えば、祖父の代に買って占有を取得したことと、父の代を経て現在の相続人が占有することを証明すれば、その間は占有が継続したものと推定される
5 推定を活用する状況の典型例(参考)
推定を活用する状況の典型例(参考)
6 推定の意味(覆滅可能)
推定の意味(覆滅可能)
あ 推定の意味→反対事実の立証による覆滅可
ア 昭和58年最判
推定であるから、これに反する事実が証明されれば、推定はくつがえされる
※最判昭和58年3月24日民集37巻131頁
イ 昭和54年最判
取得時効の成立を争う者において占有者に所有の意思がないことを主張立証すべきである
※最判昭和54年7月31日
い 覆滅の判定例(否定した判例)
占有者(弟)が所有者(兄)に対し、その土地の所有権登記移転を求めていなかったり、その土地の固定資産税を負担していなかったという事情だけでは、推定をくつがえす反証としては十分でない
※最判平成7年12月15日民集49巻3088頁
7 推定の及ばない範囲→「無過失」
推定の及ばない範囲→「無過失」
期間10年の取得時効を主張する者は無過失を立証する必要がある
例=無効の売買に基づいて物を占有する買主は、善意(売買を有効であると誤信)であると推定されるが、その誤信が無過失であるとは推定されない
※最判昭和46年11月11日判時654号52頁
8 関連テーマ
(1)取得時効の基本
詳しくはこちら|取得時効の基本(10年と20年時効期間・占有継続の推定)
9 参考情報
参考情報
本記事では、占有の態様と継続の推定について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に占有の態様と継続の推定に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
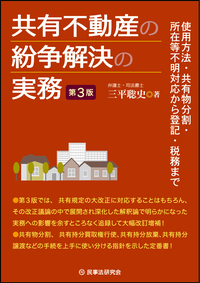
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!





