【境界標(石・杭)の設置には隣地所有者の承諾が必要だが裁判もできる(事例解説)】
1 境界標(石・杭)の設置には隣地所有者の承諾が必要だが裁判もできる(事例解説)
隣接する土地の境界(筆界)に関するトラブルはとても多いです。主なトラブルは境界の位置ですが、これに付随して境界標(境界の目印)の設置に関するトラブルもあります。本記事では具体的事例を元にして説明します。
2 事案
隣地との境界が曖昧で、境界標の設置を考えています。
隣地所有者に提案したところ、設置自体には反対していないものの、設置方法や費用負担について意見が合わず、話が進みません。
3 境界標設置の法的根拠
境界標の設置は土地所有者間の将来的な紛争を防ぐための重要なアイテムです。境界標の設置については、民法223条、224条に方法や費用分担が定められています。本事案の解決ではこれらを活用することになります。
4 隣地所有者が協力を拒否する場合
隣地所有者が当初は話し合いに応じていたものの、後に連絡を無視するようになったというようなケースはよくあります。
民法223条の権利は「協力請求権」という解釈が一般的です。隣地所有者に協力を求め、それに応じない場合には訴訟によって協力を請求する、という流れになります。「独断的に境界標を設置して事後に費用分担を請求する」ことを認める見解もありますがリスクが高いです。
具体的には、まずは内容証明郵便を送付して正式に協力を要請し、それでも応じない場合には協力請求訴訟の提起を検討します。判決を獲得すれば、仮に相手方が協力しなくても一方的に設置工事を行い、費用(の一部)を請求することができます。
5 境界位置自体に見解の相違がある場合
話し合いを続けるうちに、当事者間で境界の位置自体についても見解の相違が明らかになることがあります。このような状況では以下のような対応が必要となります。
民法223条・224条は、境界そのものについては争いがなく、単に界標を設置するかどうかについての規定です。境界自体に争いがある場合は、まず最初に「筆界確定の訴え」や「筆界特定制度」を利用して境界を確定させることが必要となります。
6 境界標の材料(材質)の選定方法
訴訟を提起する場合、境界標の材料(材質)が問題となることがあります。例えば、一方は高価な花崗岩を希望し、他方は安価なコンクリートを希望するような場合です。
境界標の材料選定は、原則として地方の慣習に従って適切なものを定めることが基本です。通常は石の標柱が用いられますが、耐久性や視認性を考慮して選定することが重要です。
当事者の協議で材料が決まればよいですが、決まらない場合、(前述のように)訴訟を提起し、最終的には裁判所が境界標の材料を決めることになります。裁判所は土地の状況、付近における慣習、費用等を総合的に考慮して適当な材料を選定します。例えば東京地判昭和39年3月17日では、境界標の材質、サイズを花こう岩造りの5寸角、長さ5尺と決定しました。
7 費用負担の問題
(1)境界標の設置費用→均等
隣接する2つの土地の面積に大きな差がある場合(例:A所有土地が300㎡、B所有土地が100㎡)、費用負担に影響するでしょうか。
民法224条本文により、境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するのが原則です。これは相隣者が境界標について同一の利益を有するという考えに基づいています。
(2)測量費用→面積比例
ただし、測量費用については、民法224条ただし書により、土地の広狭(面積)に応じて分担することになっています。
上記の例では、測量費用についてはAが75%、Bが25%を負担することになります。なお、ここでいう「測量」とは、土地の広さを計測するものではなく、単に技術的に境界線(の位置)を明瞭にするために必要な測量を意味します。たとえば、すでに地積測量図があり、その図面を実際の土地に復元するための作業のことです。
8 既存の境界標の意味→正確とは限らない
土地に先代の時代に設置されたと思われる古い境界標があり、隣地所有者がその位置を承認しない場合の対応も考える必要があります。
境界標は境界を確定する効力を有せず、裁判官が境界を決定する際の一つの判断材料としての意義を有するにとどまります(最判昭和31年12月28日)。境界紛争が起きた場合は、境界標だけでなく登記情報、公図、測量図、占有状況など他の証拠と併せて総合的に判断されます。
つまり、境界標は、設置した時点では境界の位置を正確に反映していたはずですが、長年が経過すると正確だとは言い切れない扱いとなる、ともいえます。
9 筆界確定後の境界標設置の問題
筆界確定訴訟を経て境界(筆界)が確定すれば、一件落着です。判決書の内容を現地に復元すれば、境界の位置が判明する状態になっています。とはいっても、実際に現地に境界標を設置しないと分かりにくいです。ただし、「判決を元にして境界標を強制的に設置する」ことはできません。両当事者の協力が必要です。
まずは判決内容を示して境界標設置の協力を要請することが重要です。それでも協力が得られない場合は、前述の、境界標設置の協力請求訴訟の提起を検討します。
10 まとめ
境界標の設置は、将来の土地に関する紛争を予防するために非常に重要な手続きです。境界自体に争いがなければ民法223条・224条に基づいて対応し、境界に争いがある場合は筆界確定の手続を先行させることが肝要です。
11 本記事で活用した法的知識の詳細
詳しくはこちら|境界標の設置と費用負担(民法223条・224条)(解釈整理ノート)
本記事では、境界標の設置やその費用負担について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に土地の境界(筆界)や境界標に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
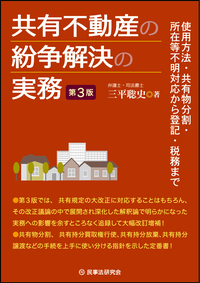
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!





