【質権の総則規定(民法342条〜351条)(解釈整理ノート)】
1 質権の総則規定(民法342条〜351条)(解釈整理ノート)
マイナーな担保物権として質権があります。質権に関するルール(条文)のうち、各種の質権に(ほぼ)共通するものが総則である民法342条〜351条です。本記事では、これら条文について、規定の内容や解釈を整理しました。
なお、質権を実際に活用する方法やその注意点については、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|質権の基礎と実務での活用ガイド(特徴・企業間取引の実例・手続)
2 民法342条〜351条の条文
民法342条〜351条の条文
第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(質権の目的)
第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
(質権の設定)
第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
(質権設定者による代理占有の禁止)
第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
(質権の被担保債権の範囲)
第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(質物の留置)
第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
(転質)
第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
(契約による質物の処分の禁止)
第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。
(物上保証人の求償権)
第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
※民法342条〜351条
3 質権の定義と基本性質(民法342条)
(1)民法342条の規定内容
民法342条の規定内容
(2)質権の基本的効力
質権の基本的効力
あ 留置的効力
債務者の弁済を心理的に促す効力
い 優先弁済的効力
目的物の換価により他の債権者に先立って弁済を受ける効力
(3)質権の付従性
質権の付従性
あ 基本
質権は被担保債権の弁済のためだけに存在する権利である
い 被担保債権の制限→なし
被担保債権に制限はなく、金銭債権以外の債権も担保できる
条件付・期限付債権も担保することができる
被担保債権が存在しない根質(将来債権のための質権)も有効とされている
※大判大正6年10月3日民録23輯1639頁(根質について、被担保債権の最高額の決定は不要とした判例)
4 質権の目的→譲渡可能な物・権利(民法343条)
質権の目的→譲渡可能な物・権利(民法343条)
あ 規定内容
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない
い 譲渡できない物(権利)の具体例
ア 動産の例
模造通貨・国債、麻薬、毒物・劇物などの禁制品
イ 財産権の例
譲渡禁止の特約がある債権など
5 質権の成立→要物性(民法344条)
質権の成立→要物性(民法344条)
あ 民法344条の規定内容
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる
い 質権契約の性質→要物性
質権は要物契約であり、合意だけでは成立せず、引渡しが成立要件となる(物権設定における例外)
う 「引渡」の内容→占有改定は除外
「引渡し」には占有改定(民法183条)は含まれない
設定時に占有改定した場合、質権は効力を生じない
6 質権設定者による代理占有の禁止(民法345条)
質権設定者による代理占有の禁止(民法345条)
あ 民法345条の規定内容
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない
い 設定後の目的物返還→動産は対抗力消滅、不動産は影響なし
質権設定後に質物を設定者に返還した場合、動産質権は対抗力を失うが、不動産質権は影響を受けない
※大判大正5年12月25日民録22輯2509頁
7 質権の被担保債権の範囲(民法346条)
質権の被担保債権の範囲(民法346条)
あ 民法346条の規定内容
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する
ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない
い 質権の不可分性
本条に列挙されている債権は、すべて質権によって担保される
質権者は、これらの債権の全部が弁済されるまで目的物の全部についてその権利を行うことができる
う 「元本」の意味→被担保債権
「元本」とは(一般的な用法とは異なり)質権によって担保されるべき債権それ自体を意味する
え 「利息」の意味
「利息」とは、(狭義の)被担保債権を元本として、その使用の対価として、元本に対して一定の割合で支払われるものを意味する
8 質物の留置(民法347条)
質物の留置(民法347条)
あ 民法347条の規定内容
質権者は、被担保債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる
ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない
い 物権の性質→第三者に主張可
留置的効力は物権として第三者にも主張できる
う 競売(強制競売・担保権実行)における取扱い
ア 不動産質権
使用収益をしない旨の定めのない最優先順位のものだけが存続する
イ 動産質権
質権者が占有する動産は第三者による差押えを拒むことができる
え 質権者の保管義務
善管注意義務をもって目的物を占有する
承諾なく使用・賃貸することはできない(不動産質権の例外あり)
お 質権者の果実の収取権利
質権者は果実を収取し、まず利息に充当し、次に元本に充当する(不動産質権の例外あり)
9 転質権(民法348条)
転質権(民法348条)
あ 民法348条の規定内容
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる
この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う
い 2種類の転質
ア 責任転質
設定者の承諾なく質権の範囲内で転質できる権利
イ 承諾転質
設定者の承諾を得て転質する場合、その効果は承諾内容による
10 流質契約の禁止(民法349条)
流質契約の禁止(民法349条)
あ 民法349条の規定内容
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない
い 適用範囲→弁済期前のみ
弁済期後の流質契約は有効である
う 流質契約違反の効果
流質特約は無効となるが、質権自体は一般に有効である
え 例外
ア 商事質権
商行為による債権を担保する質権は流質契約が許される
イ 営業質
質屋営業法による質屋は流質契約が許される
お 譲渡担保の有効性(参考)
譲渡担保は、流質契約と同じ効果を有する点に問題があるが、判例・学説は、これを有効と解している
11 物上代位(民法350条)
物上代位(民法350条)
あ 民法350条の規定内容
質権にも留置権及び先取特権の規定(民法296条から300条まで及び304条)が準用される
い 準用する規定の内容
ア 留置権規定の準用
質権の留置的効力に留置権の規定が準用される
イ 物上代位
質権も物上代位が認められる(「債務者」は「質権の目的物の所有者」と読み替える)
12 物上保証人の求償権(民法351条)
物上保証人の求償権(民法351条)
あ 民法351条の規定内容
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する
い 物上保証人の特徴→債務なし
物上保証人は債務を負わない点で保証人と異なる
う 求償権の内容→保証人と同じ
求償権については保証人と同様に扱われる
13 参考情報
参考情報
本記事では、質権の総則規定について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に質権などの担保権や債権回収に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
共有不動産の紛争解決の実務第3版
使用方法・共有物分割・所在等不明対応から登記・税務まで
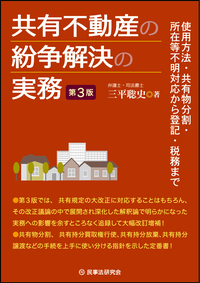
共有不動産をめぐる法的紛争の解決に関する実務指針を
《事例》や《記載例》に即して解説する実践的手引書!
- 第3版では、共有規定の大改正に対応することはもちろん、その改正議論の中で展開され深化した解釈論により明らかになった実務への影響を余すところなく追録して大幅改訂増補!
- 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分ける指針を示した定番書!
- 相続や離婚の際にあわせて問題となりうる「共有者の1人による居住」「収益物件の経費・賃料収入」「使っていない共有不動産の管理」の相談対応や、「空き家」「所有者不明土地」「相続未登記」問題の解決のヒントに!
- 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!





