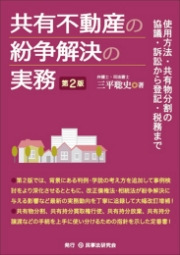【共有者から使用承諾を受けて占有する第三者に対する明渡請求】
1 共有者から使用承諾を受けて占有する第三者に対する明渡請求
共有者の1人から共有物を使用(占有)することの承諾を受けて、第三者が共有物を使用(占有)しているケースはよくあります。他の共有者も了解していれば問題はないですが、関与していない場合には、自身が使用できないことになるので、明渡や金銭の請求をするという発想が生じます。本記事では、明渡請求についての法的問題を説明します。
2 明渡請求→否定(昭和63年最判の事案と判断の要点)
共有者の一部Xから使用することの承諾を受けて第三者Zが共有物を使用している場合、他の共有者(非承諾共有者)Yは、自身が使用できない状態になっているので権利を侵害されているといえます。しかし、昭和63年最判は、承諾した共有者Xが使用しているのとみなす、という理論を採用しました。では、共有者X自身が共有物を占有している状況を想定しましょう。この場合どうなるかというと、明渡請求は原則として否定されます。
詳しくはこちら|共有物を使用する共有者に対する明渡・金銭の請求(基本)
結論として、第三者Zは退去する必要はない、ということになります。
明渡請求→否定(昭和63年最判の事案と判断の要点)
あ 共有者による使用承諾
不動産をX・Yが共有している
不動産の使用方法についてX・Yは意思決定をしていない
Yが第三者Zに不動産の使用を承諾した
Zが不動産を占有・使用している
XがZに対して明渡を請求した
い 共有者に対する明渡請求(前提)
Y自身が共有物を占有している場合
→Yの占有はYの共有持分権に基づく
→XはYに対して明渡を請求できない
※最判昭和41年5月19日
詳しくはこちら|共有物を使用する共有者に対する明渡・金銭の請求(基本)
う 第三者に対する明渡請求→否定
XはZに対しても明渡を請求できない
※最判昭和63年5月20日
3 昭和63年最判の引用
前述の昭和63年最判が採用した理論はどのようなものでしょうか。占有する第三者Zと非承認共有者Yの関係は、共有者(XY)間の関係が妥当するという理由が示されています。共有者間の明渡請求については昭和41年最判が原則として否定する結論を出していますので、昭和63年最判では昭和41年最判を引用して、これと同じ結論になる、つまりZへの明渡請求を否定する、ということが示されています。
昭和63年最判の引用
なお、このことは、第三者の占有使用を承認した原因が共有物の管理又は処分のいずれに属する事項であるかによつて結論を異にするものではない。
※最判昭和63年5月20日
4 昭和63年最判の読み取り方→同視理論の採用
昭和63年最判の判決文には、「みなす」「同視する」という言葉はないですが、同視する理論を採用したと読み取れます。実は、この判例が出る前には、他にも見解があったのですが、昭和63年最判が同視理論(みなす理論)を採用して、実務における見解を統一したのです。
昭和63年最判の読み取り方→同視理論の採用
あ 判例の評釈
ア 富越和厚氏見解
・・・第三者の占有は固有の正当権原に基づくものではないとしても、それが多数持分権者の持分権に基づく利用権から発し、多数持分権者の利用と同視しうるという点に、この判例法理の根拠を求めるべきであろうし、そうとすると第三者の占有を承諾したのが少数持分権者であっても、共有者間の場合に関する判例法理により、同様の結論を採るべきことになるから、第三者の占有が共有者の持分に基づく利用権から発し、当該共有者の利用と同視しうるときは、他の共有者は、持分の多寡にかかわらず、第三者と承諾共有者との原因契約又は承諾共有者の利用権が消滅しない限り(注・(後記※2))、当然には明渡しを求めることができないという結論になろう(石田・判夕五〇五号三八頁は、共有者間に関する判例法理から右の判例の結論は当然であるとする)。
※富越和厚稿『共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否』/『ジュリスト918号』1988年9月p79
イ 齊木敏文氏見解
・・・共有者の一人から占有使用を承認された第三者に対する明渡請求を認めると貸与者たる共有者の持分権を完全に否定したことになるので、共有者とこの第三者を同視して判旨の結論になったのであろう・・・。
※齊木敏文稿『共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否』/『判例タイムズ706号臨時増刊』p37
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p61(同趣旨)
い 令和3年改正における議論(参考)
(注8)②及び③に関し、共有者が第三者に当該共有物を使用させている場合には、共有者が共有物を使用していると評価する。
※民法・不動産登記法部会『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案』2019年12月p2
5 原因行為の処分・管理の分類と明渡請求の関係
ところで、共有者が第三者に共有物の使用を承諾する理想的方法は、共有者全員で協議して意思決定をした上で、共有物の賃貸借、使用貸借や地上権設定(原因行為)として第三者と契約を締結するというものです。これらは共有物の変更(処分)または管理行為に分類され、共有者全員または持分の過半数で決定することになります。
詳しくはこちら|共有物の賃貸借契約の締結の管理行為・変更行為の分類
詳しくはこちら|共有物の使用貸借の契約締結・解除(解約)の管理・処分の分類
そこで、承諾したいと思っている共有者が持分の過半数を有していなければ賃貸借や使用貸借の契約をすることについての意思決定はできません(仮に過半数の持分を有していたとしても、協議や多数決を行っていない場合は意思決定として認められないこともあります)。
ところが、昭和63年最判は、このような原因行為が無効(非承諾共有者に対抗できない)であるにも関わらず、明渡請求を否定しているのです。
なお、共有者が単独で、自身が有する共有持分についてだけ使用貸借や賃貸借契約を締結するという発想もありますが、これは否定されています。
原因行為の処分・管理の分類と明渡請求の関係
あ 富越和厚氏見解
第三者の占有承諾が管理行為に属する行為によるものである場合でも、管理に関する協議がされていない以上、非承諾共有者に右管理行為を対抗することができるものではないから、承諾共有者が多数持分権者であったとしても、そのことから当然に第三者の占有が正当視されるものではない。
したがって、第三者の占有を承諾した共有者の行為が処分行為であるか、管理行為であるかを区別する意味はないことになる。
※富越和厚稿『共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否』/『ジュリスト918号』1988年9月p79
い 原田純孝氏見解
(2)そのうえで、最高裁は、右の考え方を、
「共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者」とその余の共有者との関係にも直接的に適用する。
⑦その第三者の占有も、一部共有者の持分に基づくものと認められる限度では、それを承認した一部共有者自身による占有使用の場合と同等の性質(すなわち上記の①~③の性質)をもつというのがその理由である(昭和六三年判決の判旨の後段部分参照)。
これは、一部共有者のもつ共有物の占有使用権原が、いわばそのままの性質をもって第三者の占有使用のうえに乗りうつること――ないしは、その第三者の占有使用を一部共有者による占有使用と同視しうること――を認めたものといえる(富越・前掲解説七九頁)。
だからこそ、
⑧右の第三者の占有使用が保護されるためには、一部共有者による「占有使用の承認」があったことで足り、その原因行為が共有物の管理または処分のいずれに属するものであるかは問題外とされることになるのである。
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p61
う 共有持分と対象とする賃貸借・使用貸借(参考)
共有持分を対象(目的)とする賃貸借・使用貸借契約は認められない
詳しくはこちら|共有持分権を対象とする処分(譲渡・用益権設定・使用貸借・担保設定)
6 使用承諾の解除による明渡請求→否定方向
昭和63年最判が明渡請求を否定する根本的理由は、共有者による使用承諾があることです。そこで使用承諾を後から解除(解消)した場合には、明渡請求が認められるのではないか、という発想があります。
しかし、使用承諾は純粋な事実行為であり、共有者全員の関与があれば民法の規定(252条など)により解消できる、というものではないと思います。原田純孝氏は、昭和63年最判の理論を前提とするとそのような解釈になる、という方向性を示しています。
使用承諾の解除による明渡請求→否定方向(※2)
あ 使用承諾の解除→明渡請求可能(前提)
(v)昭和六三年判決の第一、第二審や富越・前掲解説七九頁は、Xの側で主張・立証すべき理由たりうる事由として、「契約が解除等によって消滅したこと」(ないしは、原因契約または利用権の消滅)を例示している。
同判決の事案では、Yの使用借権が、それに承認を与えた一部共有者との間でも消滅すればYは単純な無権原者となるという意味では、正当であろう。
い 持分の過半数による解除の決定の可否→否定方向
しかし、問題は、その解除がどうやってなされうるかにある。
非占有共有者が多数持分権者であれば、協議による意思決定によって少数持分権者のした賃貸借等を解除することができるのであろうか。
前掲最判昭和二九年三月一二日や同昭和三九年二月二五日によれば、肯定されるかのようにみえる(金山・前掲判批九一頁はこの立場をとく。また、鈴木・前掲書二七頁参照)。
共同相続人の一人が従前からの占有使用を継続しているような場合とは利害状況が違うから、あるいはそれでよいのかもしれない。
こう解すれば、現実の占有使用者が一部共有者の承認を得た第三者である場合に限って、二五二条本文の規定が直接生きてくるということになる。
しかし、非占有共有者が少数持分権者でしかない場合との格差が大きすぎるような気がしないでもない。
また、多数持分権者がその一存で共有地に第三者のための地上権を設定した場合には、判例(最判昭和二九年一二月二三日民集八巻一二号二二三五頁)によれば、その地上権は少数持分権者との関係でも無効になるはずであるが、このときには少数持分権者からの明渡請求が認容されるのかという問題もある。
第三者の利用権が不存在であるということを前提として、右の(v)の考え方を適用すれば、肯定されてよいようにもみえるが、本稿で扱った判例理論からすれば――第三者の占有使用が一部共有者の承認に基づくことには変わりがないのだから――反対に解されるようにもみえる。
これらについては、なお最終的な判断を留保しておきたい。
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p63、64
う 占有権原の特徴→「事実行為」により発生(参考)
というのは、そこからは、この理論によって保護されるのは、少なくとも一部共有者の意思に基づいた共有物の占有使用という一種の事実行為であって、その法律的根拠や権原性質の如何はそこでは第二義的な問題にすぎないことを推測することができるからである。
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p61
7 効力を生じない賃貸借・使用貸借と使用承諾→包含理論
ここで、共有者XYのうちX(だけ)と第三者Zが賃貸借契約を締結したことを想定します。そしてこの賃貸借は変更(処分)分類(共有者全員の同意が必要)であったとします。共有者Yは賃貸借に同意していないので、無効(賃借権発生という効果を生じない)となります。
では、Yが共有持分権に基づいてZに対して明渡請求をしたら、これは認められるのでしょうか。
確かに、Zは(抗弁1として)賃借権という占有権原を主張しても認められません。しかし、共有者Xによる使用承諾という占有権原(の抗弁2)はどうでしょう。
昭和63年最判の読み取り方を前提とすると、(抗弁として)認められるように思われます。つまり、賃貸借契約は、賃借権発生という効果は生じないけれど、使用承諾という効果は生じる(「賃貸借」の合意に使用を承諾したという事実が含まれる、大は小を兼ねる)といえると思います。
ここまでの理論どおりであれば、Zは(抗弁2が認められることによって)明け渡す義務はないということになります。
このように、賃貸借の合意の中に使用承諾の事実が包含されるという判断をした実例はみあたりません(判例としてはブランクです)。この点、売買の合意の中に使用承諾の事実が包含される、という結論をとった判例はあります。次に説明します。
効力を生じない賃貸借・使用貸借と使用承諾→包含理論
あ 山田誠一氏指摘→判例の準則の不存在(参考)
また、共有不動産を占有使用することの承認が、売買契約(6判決(注・最判昭和57年6月17日))である場合の他に、賃貸借契約あるいは使用貸借契約である場合にも適用されるかという問題がある。
この問題についての判例の準則も、ブランクであるというべきである。
※山田誠一稿『共有不動産の占有に関する法律関係―森林法一八六条違憲最高裁判決を機縁にして―』/『判例タイムズ641号』1987年10月p47
8 共有者単独で共有物を売却したケースにおける明渡請求→否定
共有物(全体)の売却は、共有者の全員が売主とならなければできません。
詳しくはこちら|共有物の変更行為と処分行為の内容
共有者の一部だけで共有物全体を売却してしまった場合には、原則として売主の共有持分だけが移転し、売主になっていない共有者の共有持分については他人物売買の状態になります。
詳しくはこちら|共有者単独での譲渡(売却)・抵当権設定の効果(効果の帰属・契約の効力)
この点、共有持分(所有権)とは別に、占有の問題が生じます。
昭和57年最判がこの問題について判断を示しています。事案は、XY共有の土地の一部を共有者の一部(Xだけ)が買主Zに売却した、という少し特殊なケースです。
まず、売買の対象部分が特定されていないことから、共有持分の移転も生じない、という判断が示されています。つまり、買主Zは共有者でもない、ということになりました。
そうすると、Zには占有権原がないので、Yによる明渡請求が認められるように思えますが、最高裁は、Zの占有は共有者Xの承認に基づくので、明渡請求は否定される、と判断します。
つまり、売買契約は、物権の移転が生じない(その意味では無効)であるけれど、売買契約(合意)の中に使用承認(承諾)の事実が含まれる、という判断をしたといえます。
その上で、最後に、共有者の使用承諾を得た第三者への明渡請求を否定するという結論を出しています。
なお、昭和63年最判は、昭和57年最判をより一般化した、という位置付けになっています。
共有者単独で共有物を売却したケースにおける明渡請求→否定
あ 事案と結論の要点
ア 売買契約と引渡
土地をX・Yが共有していた
Yが土地の一部をZに売却した
YがXに当該土地(売買の対象)を引き渡した
買主Zは土地上に建物を建てた
XはZに対して土地明渡を請求した
イ 結論
Xの明渡請求を認めない
い 占有権原→共有者の使用承認(判例の引用)
右事実によれば、被上告人は、Kとともに、本件土地について四分の三の持分権を有する共有者から本件土地の南側部分約六〇坪を買い受ける旨の契約を締結し、具体的な土地の範囲及び代金額の確定を将来に残したまま、おおよその部分の引渡を受け、同部分の地上に本件建物を建築したものであつて、本件建物の所有による被上告人の右敷地占有は、四分の三の持分権を有する共有者との間の売買契約の履行過程における右共有者の承認に基づくそれであるということができる。
※最判昭和57年6月17日
9 夫婦間の同居義務による占有権原を使用承諾と扱った裁判例
実際に共有者が第三者(共有者以外の者)に使用することを承諾したわけではないケースでも、この理論が使われることがあります。その一例は、夫婦という関係性によって占有権原が認められるケースです。共有者が夫X1とその父X2であり、占有者である妻Yに対する明渡請求で(X2からYへの明渡請求の部分について)この理論が使われました。
夫婦間の同居義務による占有権原を使用承諾と扱った裁判例
あ 夫婦間の同居義務による占有権原(前提・概要)
夫所有の建物に妻が居住するケースにおいて、妻は同居義務に基づく占有権原が認められる
夫からの明渡請求は認められない
詳しくはこちら|夫婦間の明渡請求(民法752条に基づく居住権)
い 共有者による使用承諾理論の適用
ア 共有者による使用承諾理論(昭和63年最判)
・・・共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は上記第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である(最高裁昭和63年5月20日第二小法廷判決・裁判集民事154号71頁)。
イ 夫婦間の同居義務による占有権原を使用承諾として扱う
そうすると、前記(2)で説示したとおり、被告は、原告X1の本件建物の共有持分について、夫婦の扶助義務に基づいて、これを使用する権原を有すると認められるのであり、原告X1の共有持分に基づくものと認められる限度で本件建物を占有使用する権原を有するものであるから、原告X2は、被告に対しては本件建物の明渡を請求することはできず、また、原告X2の持分が本件建物の10分の1であること(前記前提事実(2))、原告X2が原告X1の実父であり、被告の義父に当たるものであること(前記前提事実(1))からすれば、さらに、全証拠及び弁論の全趣旨に照らしても、例外的に原告X2の本件建物の明渡請求を認めるべき特段の事情も認められない。
※東京地判平成30年7月13日
10 使用方法の意思決定を行った上での明渡請求
昭和63年最判の判断は、共有物の使用方法についての意思決定がなされていないことを前提としています。そこで、使用方法の意思決定を行って、第三者の使用が共有者による決定内容に反する状態にすれば明渡請求が認められるはずです。これについては、共有者の1人が共有物を占有しているケースで、使用方法の意思決定に反する場合には明渡請求が認められるのと同じことです。
詳しくはこちら|共有物を使用する共有者に対する明渡・金銭の請求(基本)
違う見方をすると、昭和63年最判は、共有者間で使用方法の協議(と意思決定)がなされていないために、明渡請求が否定されたともいえます。これは、協議というプロセスを遂行していない限り意思決定の効果は生じないという見解を意味していると読み取れます。
詳しくはこちら|共有物の使用方法の意思決定の方法(当事者・協議の要否)
使用方法の意思決定を行った上での明渡請求
あ 前提事情
共有物の使用方法について、共有者間で意思決定がなされていない
い 意思決定を行った後の明渡請求
・・・非承諾共有者が多数持分権者であるときは、第三者の占有使用を認めない旨の協議に基づき第三者に対して明渡しを求めることができる(承諾共有者は第三者に対して債務不履行の責を負う)。
※富越和厚稿『共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否』/『ジュリスト918号』1988年9月p79
※青木敏文稿『判例タイムズ706号 昭和63年度主要民事判例解説』1989年10月p37参照
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p63参照
11 承諾を得た第三者が使用する場合の金銭請求(概要)
以上のように、共有者Aが第三者Cに使用を承諾した場合、共有者Bによる明渡請求は原則として認められません。その代わり、Bは、AやCに対して金銭(使用対価)の請求をすることが認められます。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有者から使用承諾を受けた第三者が占有するケースにおける金銭請求
本記事では、共有物(共有不動産)を共有者以外の者が使用しているケースにおける明渡請求について説明しました。
実際には具体的な状況によって結論が違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。